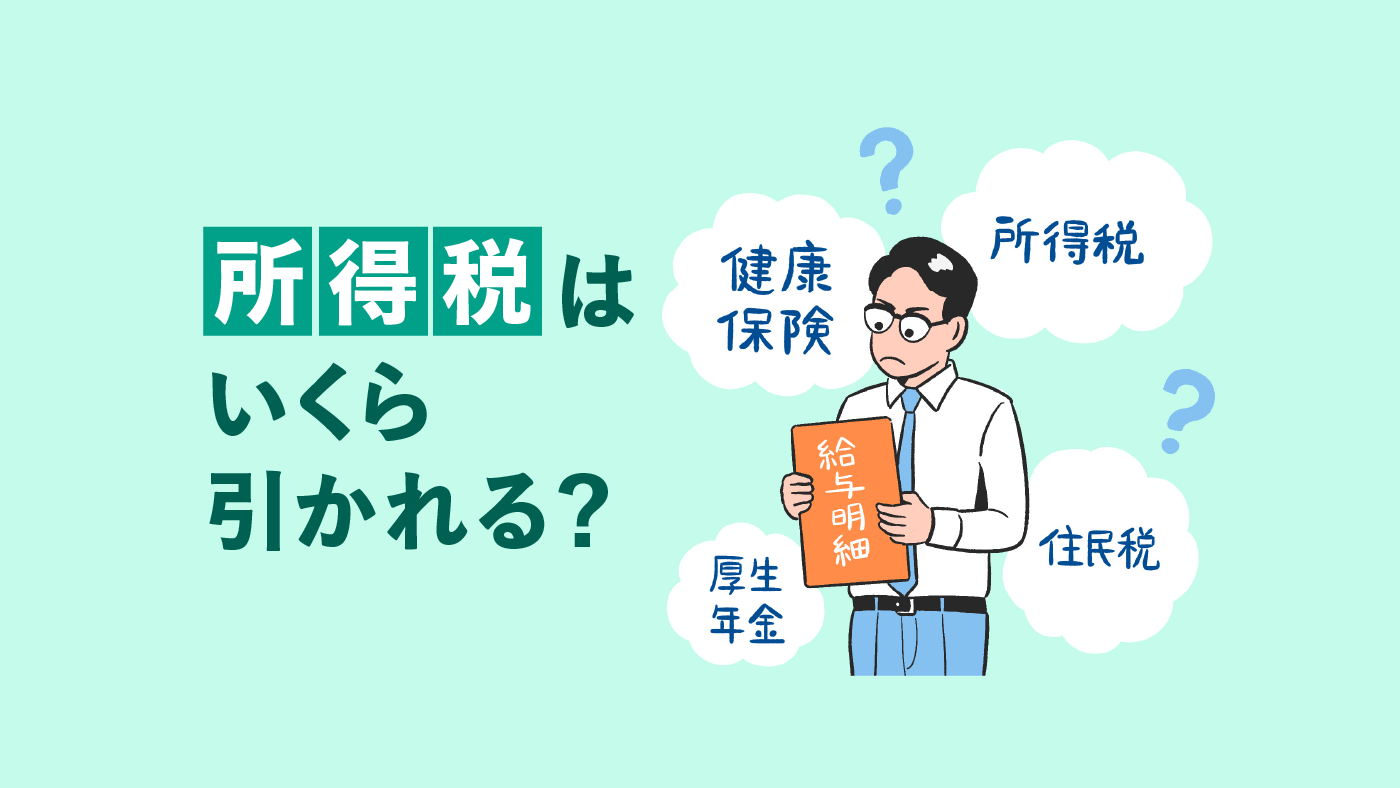相談内容「なかなかお金を貯められません。教育費はいくら必要ですか?」
夫は年収600万円の会社員、私は専業主婦で、2人とも40代です。小学生の子どもが1人います。住宅ローンの返済が月10万円、保険料の支払いが月3万円ほどあります。
毎月のやりくりはなんとかできていますが、貯金が苦手でなかなか貯められません。ママ友から「これから教育費がかかってくるから今のうちに貯めておいた方が良い」と聞いて焦っています。
教育費は具体的にはいくらくらい必要で、どうやってその金額を貯めれば良いのか教えて下さい。
必要な教育資金を確実に貯めるための3つのステップ

Aさんのように「教育費が足りなかったらどうしよう」と不安になる人は少なくありません。学費を始め、さまざまなものの値上げに関するニュースを見聞きする機会も増え、余計に心配になってしまうのではないでしょうか。
必要な教育資金を確実に貯めるためには、次の3つのステップを順番にクリアしていくと良いでしょう。
ステップ①収支を把握し、家計を見直し、黒字額を増やす
「お金が貯められない」ということは、毎月入ってくるお金(収入)と毎月出ていくお金(支出)の差がほとんどない状態(もしくは赤字家計)になっている可能性が高いと考えられます。まずは、家計の改善を試みましょう。
収支を把握し、家計を見直せば、黒字額を増やせるでしょう。ただし、黒字額を増やすには、「①収入を増やす」「②支出を減らす」の2つの方法しかなく、裏技や近道はありません。地道に家計改善に取り組みましょう。
【お金がたまらない原因】
Aさんの家庭は、なぜお金が貯まらないのでしょうか。
世帯年収は600万円とのことですが、この金額は平均と同程度もしくは少し多いくらいの水準なので、「収入が少な過ぎて貯められない」というわけではなさそうです。
Aさんの家計で最も大きな支出は、月10万円の住宅ローンの返済です。これは手取りの25%程度に相当し、無理なく返済できる範囲内と言えます。よって、「無理なローンを組んだために家計が厳しい」というのも違うようです。
もう1つ分かっている支出が月3万円ほどの「保険料」です。子育て世帯は保険の重要性が高いと言えますが、保険の掛けすぎには注意が必要です。掛けすぎた保険を見直したり、目的に合わせて終身保険ではなく、保険料が割安な収入保障保険などを活用することで、節約できる可能性があります。
Aさんはまだお子さまが小学生なので、一般的には貯めやすい時期と言えます。教育費以外の支出が不明、つまり把握できていない状態なら、貯まらない原因がそこにある可能性が高いでしょう。
まずは、収支を正確に把握することを心がけましょう。家計簿やアプリで収支を記録するのがおすすめです。
【支出を減らすために押さえておくべきポイント】
支出を把握したら、無駄遣いがないか、節約できそうなポイントがないか確認してみましょう。支出を減らす際に押さえておきたいのが、次の3点です。
1.金額の大きな支出から見直す
2.1回の支出よりも固定費を見直す
3.自分が価値を感じるものだけにお金を使う
節約というと、毎回のスーパーでのお買い物を工夫するといった方法を思い浮かべる人も多いですが、実は支出額が大きいものや固定費から見直した方が高い効果が期待でき、おすすめです。
例えば住宅費や保険料の他、自動車代や通信費・光熱費、習い事代など、毎月一定の支出が長く継続するものを中心に無駄がないかチェックしてみましょう。
節約は大切ですが、がんばり過ぎるあまり、何事も我慢ばかりでつらくなってしまう人もいます。全ての支出を一律に減らすよりも、自分が価値を感じるものにはお金を使うようにして、支出にメリハリを付けた方が継続しやすくなるでしょう。
【収入を増やすという選択肢も】
より貯まる家計にするためには、支出を減らすだけでなく、収入を増やすことも検討してみましょう。
例えば、Aさんは今は専業主婦ですが、パートで働いて収入を得られれば、月数万円分は家計のやりくりが楽になります。その他、副業をする、資格を取って収入アップを目指す、資産運用を行うなどの方法もあります。
ステップ②必要な教育資金を知り、貯蓄目標を設定する
次に、いくら貯める必要があるのかを知り、貯金の目標を設定してみましょう。
教育資金の金額は、教育方針やお子さまの進路によって大きく変わります。Aさんだけ、Aさん夫婦だけでなく、お子さまも交えた上で、どんな教育を受けさせたいか、どんな学校に行きたいかなど今後について家族で話し合ってみるのがおすすめです。
仮に大学まで進学するとした場合、教育資金の目安は次の通りです。ただし、近年は物価の上昇が続き、教育費も高くなっている傾向があります。目安よりも少し多めに見積もっておくと安心です。
【小学校~大学まで全て国公立の場合】
小学校、中学校、高校、大学、全て国公立の学校に通った場合、教育費の総額は約800万円が目安です。
国公立は私立よりも学費を抑えられますが、それでもこれだけの支出が発生することになります。なお、大学進学にともなって子どもが1人暮らしを始める場合は、家賃や生活費が別途かかり、学費+αの仕送りを検討する必要性が生じるため、より多くの資金が必要になります。
【小学校~大学まで全て私立の場合】
小学校から大学まで全て私立の場合、教育費の目安は総額約2,100万円です。全て国公立の場合の3倍近くの出費が発生することになります。
この進路を希望する場合は、より家計を引き締めて、しっかりと準備していく必要があるでしょう。
【高校まで公立、大学だけ私立の場合】
小学校から高校までは公立で、大学だけ私立の場合の目安は総額約1,000万円です。
全て公立に進学したケースよりは高額になるものの、全て私立の場合の半分程度の費用で済むでしょう。
このように、必要になる費用は進路次第で大きく異なります。どんな進路を想定して、そのためにいくら用意しておくのか決めておきましょう。
ステップ③計画を立て、教育資金を貯める
必要になる金額の目安が分かったら、目標金額を決め、毎月いくらずつ貯めていけば間に合うのか逆算してみましょう。
例えば「大学進学までに400万円貯めておきたい」と考えた場合、準備にあてられる期間が10年だとすると、月3.4万円ずつ貯めていけば目標を達成できる計算です。単に預貯金するだけでなく、資産運用を組み合わせれば、より少ない積立額で目標を達成できる可能性もあります。
なお、一般的にはお子さまが小さいうちは貯め時(特にお金を貯めやすい時期)と言われています。出費が多くなる貯めにくい時期もあるため、意識的に貯蓄することがおすすめです。
より教育資金を貯めやすくするためのコツ

貯蓄にはコツがあります。「貯蓄が苦手だな」と感じたら、以下のようなポイントを意識して取り組んでみましょう。
教育資金専用の口座で分けて管理する
教育資金を確実に貯めるためにおすすめなのが、教育資金を貯蓄するためだけに使う専用の口座をつくることです。銀行などの口座は無料で開設できるので、気軽に試せます。
専用の口座を用意して、普段使う預金口座とは別に管理することで、「この口座に入っているお金は子どもの将来のためのお金だから絶対に手を付けない」という意識を持ちやすくなります。
強制的にためる仕組みをつくる
貯金が苦手なら、自分で何か作業をしたり意識したりしなくても強制的に貯まる仕組みをつくっておくのが効果的です。
例えば、銀行などで提供されているサービスを利用して、給与が入金されたらすぐに貯蓄専用の口座にお金が自動的に移動するように設定しておくのも1つです。
これは「先取り貯蓄」として知られる方法で、貯蓄分を先に確保しておいて、残りの金額で生活するようにするのがポイントです。「お給料が入ったら、ついつい入った分だけ使ってしまう」という方におすすめの貯蓄方法です。
同様の理由で、勤務先の財形貯蓄制度や、強制的に保険料が引き落とされる学資保険なども検討する余地があります。学資保険は返戻率が100%を超えるものを選ぶと良いでしょう。
ただ、預貯金や保険は一般的に物価上昇に弱いため、10年以上の準備期間が取れるのであれば資産運用に取り組むのがおすすめです。
安全性と収益性のバランスを考える
教育資金の準備を考える際は、安全性と収益性のバランスを考慮するようにしましょう。
預貯金は、お金を減らさず堅実に積み立てたい場合に最適な方法です。ただ、昨今の低金利下ではお金が増えにくく、物価上昇にも弱いことがデメリットです。
一方で、投資信託や株式などの金融商品で運用する場合、預貯金に比べてお金が増える可能性があるものの、リスクもあり安全性は預貯金より低くなります。
安全性を重視して確実に貯める部分と、収益性を意識して中長期的に運用する部分をバランス良く組み合わせて準備するのが理想的な状態です。
目標を家族と共有する
貯金の目標を達成するには、1人ではなく、家族で協力して取り組むことがとても大切です。特に教育資金は、夫婦はもちろん、お子さまにも大きな影響のある重要なものです。
誰か1人が懸命に努力しても、他の家族が非協力的なら、なかなかお金は貯まりません。家族みんなで目標を決め、協力しあう体制を作りましょう。
目標達成に向けて家族それぞれが何をできるか考えたり、今どれだけ目標に近づいているのか共有したりする時間を定期的に設けるのも効果的です。
徐々にお金が貯まっていく様子を、家族みんなでゲームのように前向きに楽しめるようになれば、「貯蓄が苦手」も「将来の教育費が不安」も払拭できるでしょう。
「教育資金や老後資金を作っていきたい」
「資産運用に興味はあるけれど、何から始めたら良いか分からない」
という方は、こちらから無料診断をお試しください。
最短1分であなたに合った資産運用プランが分かります。