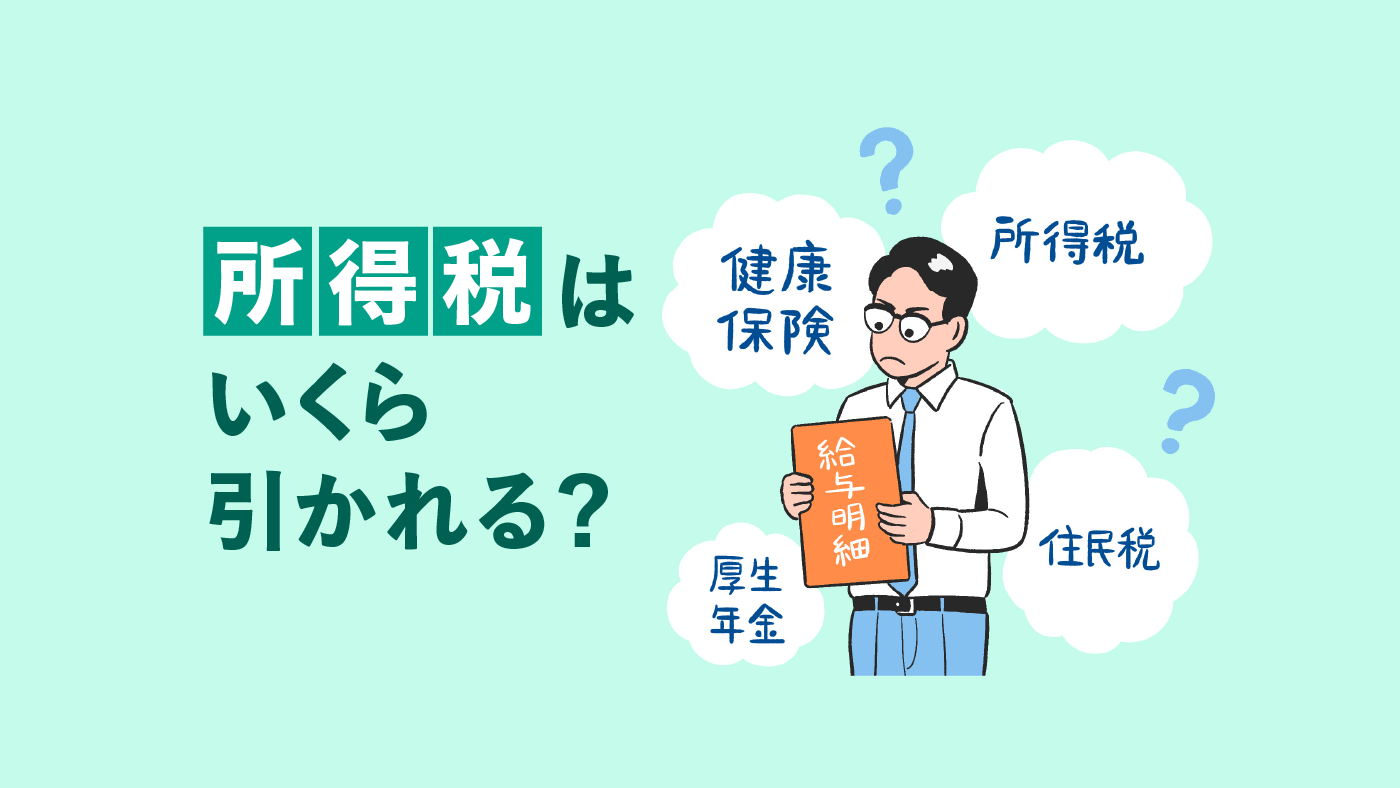勤務先から受け取る「源泉徴収票」には、さまざまな重要な情報が載っています。しかし、特にチェックせずになんとなく受け取るだけの人も多いのではないのでしょうか。
この記事では、源泉徴収票とはどのような書類で、どこを見れば何が分かるのか解説します。正しい見方を押さえて、理解を深めましょう。
源泉徴収票とは?

源泉徴収票とは、1年間に支払われた給与の総額や、そこから源泉徴収(給与天引き)で納めた税金の金額などが記載されている書類です。
通常は勤務先(源泉徴収をしている側)が毎年年末ごろに発行するもので、直近の年末調整の結果が反映されている書類でもあります。
源泉徴収票は、確定申告をする時や転職した時、ローンを組むための審査を受ける時などのタイミングで必要になります。重要な書類なので、きちんと保管しておきましょう。
源泉徴収票で確認すべきポイント
源泉徴収票を受け取ったら、確認しておきたいポイントがいくつかあります。どこをどう見れば良いのか、どの数字が何を意味しているのか、具体的に解説します。

①支払金額
「支払金額」の欄には、1年間に会社から支払われた給与の総額が記載されています。
この金額は税金や社会保険料を引かれる前の額面給与で、残業手当や住宅手当、ボーナスなども含まれています。
ここを見れば正確な年収を確認できるため、ローンの審査など収入を証明する必要がある場面で役立ちます。
②給与所得控除後の金額
②には、前述の「①支払金額」から給与所得控除を差し引いた金額(給与所得)が記載されています。
給与所得控除とは、会社員など給与を受け取っている人が利用できる控除です。自営業者などの「経費」にあたるもので、収入に応じて一定の金額を所得(税額計算の元になる数字)から差し引くことができるため、税額を抑える効果があります。
給与所得控除の金額は、以下の表に基づいて計算されます。

③所得控除の額の合計額
③には、「②給与所得控除後の金額」から各種所得控除を差し引いた金額が記載されています。年末調整の際に申告した生命保険料控除や扶養控除などが反映されています。
年末調整で申告の抜け漏れがなかったかを、内訳を見ながらよく確認しましょう。
(1)社会保険料等の金額
「社会保険料等の金額」には、1年間に支払った社会保険料(健康保険料、介護保険料、年金保険料、雇用保険料など)の総額が記載されています。
この欄にカッコ書きの数字がある場合、それは小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど確定拠出年金の掛け金)の金額を表しています。
年の途中で転職した場合や家族の社会保険料を支払った場合など、給与天引き以外で保険料を支払った時は、その金額が含まれていないことがあるため注意が必要です。
(2)生命保険料の控除額
年末調整で生命保険料控除の書類を提出した場合、この欄に控除額が記載されます。
払った保険料の金額や入っている保険の種類によっては控除額が、支払った生命保険料の総額と一致しないこともあります。生命保険料控除の控除額は決められた計算式に当てはめて計算され、最大12万円です。
生命保険料の金額の内訳も記載されているので、控除額が想定していたよりも少なかった場合は、計算式に当てはめて検算すると良いでしょう。
(3)地震保険料の控除額
年末調整で地震保険料控除の書類を提出した場合に、控除額が記載されます。
地震保険料控除の控除額は最大5万円です。加入している地震保険の保険料が年間5万円以下の場合は、その全額が控除され、この欄に反映されます。
(4)配偶者(特別)控除の額
収入が一定以下の配偶者がいる場合、配偶者控除または配偶者特別控除が適用できます。控除額は1万円~48万円で、配偶者の収入や年齢などによって決められています。
なお、納税者本人の収入も関係があります。合計所得金額900万円超だと控除額が減り、1,000万円を超えるとゼロになる仕組みです。
源泉徴収票には配偶者の氏名や配偶者の合計所得が記載される欄もあるので、併せて確認しておくと良いでしょう。
(5)控除対象扶養親族の数
配偶者以外に控除の対象になる扶養親族がいる場合、その人数が記載されます。控除の対象になる扶養親族の数が多いほど控除額が多くなり、税額が抑えられます。
扶養親族の中にも種類があり、おもに年齢によって分類されます。家族が分類上の節目となる年齢(16歳、19歳、23歳、70歳)を迎えた時や、扶養する家族の人数が変わった時は、この欄を特によく確認しておきましょう。
④住宅借入金等特別控除額
住宅借入金等特別控除額とは、住宅ローン控除の金額のことです。住宅ローン控除を利用するには、1年目のみ確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整のみで対応できます。
控除額は年末時点の住宅ローン残高の0.7%もしくは1%となっています。
住宅ローン控除は所得控除(所得から差し引くタイプの控除)ではなく税額控除(税額から直接差し引くタイプの控除)です。この欄に記載されている金額の分、税金が安くなっています。
控除額が支払うべき所得税より多い場合、源泉徴収額がゼロになっているはずです。所得税で控除しきれなかった分は、翌年度の個人住民税から控除されます。
源泉徴収票に間違いがあった場合の対処法
もし源泉徴収票を確認して間違いや漏れが見つかった場合、翌年の1月31日までなら勤務先に訂正の依頼が可能です。
1月31日を過ぎてから気付いた場合や、勤務先が修正に応じてくれない場合でも、確定申告をすれば自分で誤りを修正できます。
払い過ぎた税金の還付を受けるための確定申告(還付申告)であれば、確定申告の一般的な期日(翌年3月15日)を過ぎていても問題ありません。翌年以降5年間はいつでも手続きできるので、諦めずに申告するようにしましょう。
源泉徴収票を正しく読めるようになろう

源泉徴収票はただ受け取るだけではなく、間違いがないか確認することも大切です。特に転職やマイホームの購入、扶養する家族の増減など昨年から変化があった人は、本記事で紹介したポイントを中心によく確認するようにしましょう。
源泉徴収票の見方を理解することは、税制や社会保険制度に対する理解を深めることにもつながります。ポイントを押さえ、正しく読めるようになりましょう。
お金に関する知識を身に付けたいなら、まずは情報収集から始めませんか?
ウェルスナビにアカウント登録して頂くと、役に立つ情報をお届けします。