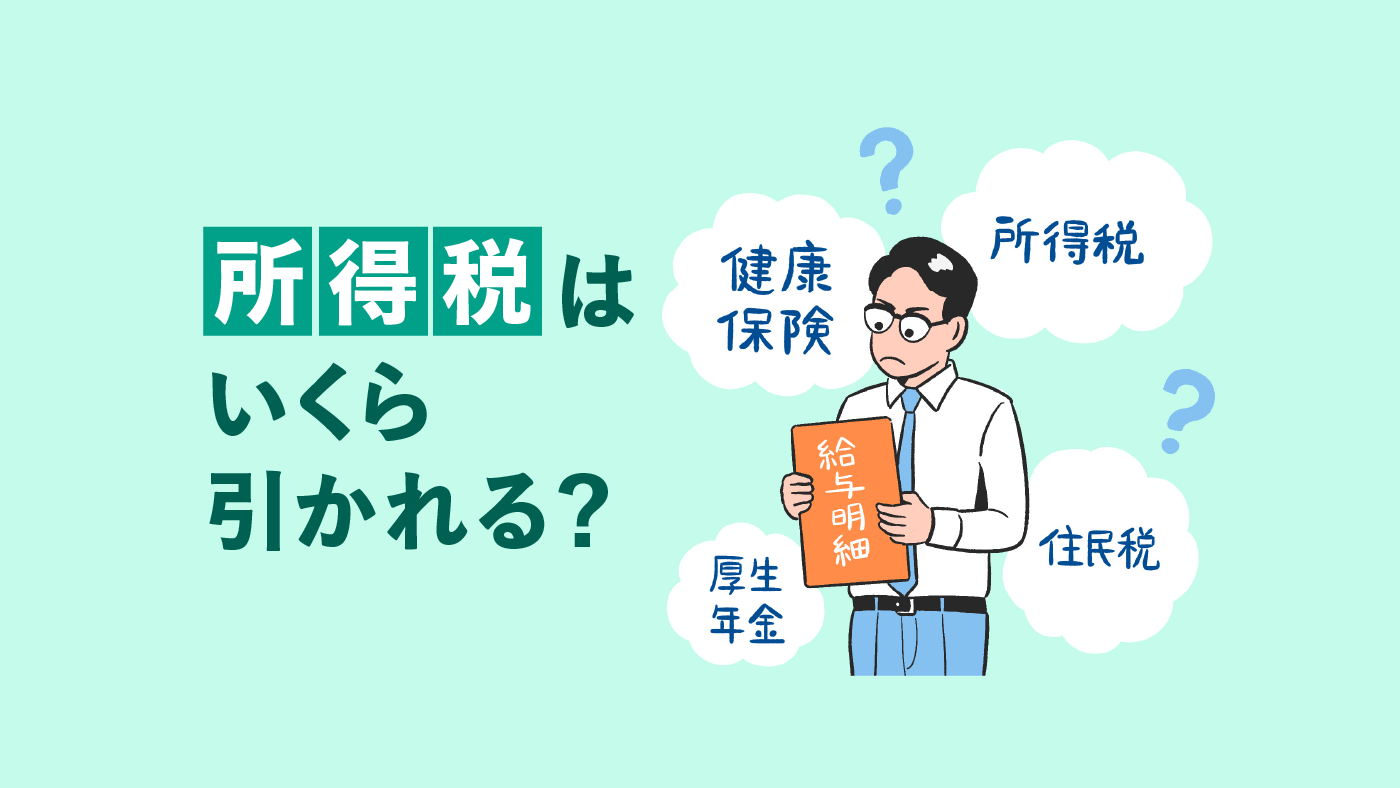老後の年金をどう受け取るかは、多くの人にとって重要な問題です。通常の受け取り方以外にも「繰り上げ受給」や「繰り下げ受給」もあり、それぞれ一長一短があります。
この記事では、公的年金の受け取り方に迷っている人に向けて、繰り上げ受給と繰り下げ受給のメリットや注意点を解説します。併せて、老後のお金の不安を解消できるよう、資産寿命を延ばす方法も紹介します。
公的年金の受け取り方は3種類
老後に受け取る公的年金(老齢年金)の受け取り方は、大きく分けて以下の3種類があります。
・法律で定められた支給開始年齢(原則65歳)から受給
・繰り上げ受給(60歳~64歳から受け取り始める)
・繰り下げ受給(66歳~74歳から受け取り始める)
年金は「ある年齢に達したら自動的に受け取れる」というものではありません。どのタイミングで受け取り始めるか自分で決めて、自分で手続きする必要があります。
65歳から受け取り始めるのが原則ですが、それより早く受け取り始めることを「繰り上げ受給」、遅く受け取り始めることを「繰り下げ受給」といいます。
繰り上げ受給を選択した場合、1ヶ月繰り上げる(早くする)ごとに年金額が0.4%減額されます。対して、繰り下げ受給では1ヶ月繰り下げる(遅くする)ごとに年金額が0.7%増額されます。

公的年金を繰り上げ受給するメリット
公的年金を繰り上げ受給する(早く受け取り始める)メリットは、以下の通りです。
収入のない期間を短くできる
繰り上げ受給は、60歳から64歳のあいだで受け取り始めるタイミングを選択できます。
例えば60歳で定年退職して収入がなくなってしまっても、年金を早く受け取り始めれば、収入のない期間を短くすることができます。それまでの蓄えや退職金が少なくても、年金収入を早めに確保できれば生活の支えになるでしょう。
何歳まで生きるかは誰にも分からないものなので、できるだけ若くて元気なうちに年金を受け取っておくというのも1つの考え方です。
公的年金を繰り上げ受給する場合の注意点
公的年金を繰り上げ受給する場合、次のような点に注意しましょう。
1年間早く年金の受け取りを開始すると年金額が4.8%減る
繰り上げ受給は、早く受け取り始める分、通常よりも1回当たりの年金額が少なくなります。
減額率は1ヶ月当たり0.4%で、1年早めて64歳から受給する場合は4.8%減る計算です。最も早く受け取るパターン(60歳受給開始)だと24%の減額です。減額された年金額は戻ることはなく、一生涯そのままの金額で支給され続けます。
なお、原則として国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(老齢厚生年金)は同時に繰り上げ請求する必要がある点が繰り下げ受給の場合と異なります。繰り上げ受給すると、どちらも1年当たり4.8%の減額になります。
働きながら年金を受け取ると、年金額の一部もしくは全部が支給停止になることがある
近年、定年退職した後や年金を受け取り始めた後も働き続ける人が珍しくありません。しかし、働きながら年金を受け取る場合、収入が一定額を超えると年金額の一部もしくは全部が支給停止になることがあります。
これは「在職老齢年金」と呼ばれる仕組みで、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る人が、仕事で得た収入と年金の合計が月50万円を超える場合は要注意です。支給停止になった分の年金は、後で収入が下がったとしても戻ってきません。
繰り上げ請求は取り消すことができない
一度繰り上げ受給の請求をしたら、その後はもう取り消すことができません。
例えば、前述の在職老齢年金制度によって年金額が減るほど収入が増えたケースなどでも「やっぱり年金の受け取りをやめる」といった選択は不可能です。
いつから受け取り始めるかの決断は慎重に行いましょう。
国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなる
受給できる年金額を増やす手段として、国民年金の任意加入や保険料の追納があります。いずれも過去に年金保険料を納めていなかった期間がある場合などに有効な手段ですが、繰り上げ受給の請求をした後は、これらを選択できなくなります。
繰り上げ受給すると、減額された年金額が確定します。「年金をもっと増やしたい」と思っても、繰り上げ受給を請求した後だと難しくなると知っておきましょう。
遺族厚生年金などの他の年金と併せて受給することはできない
繰り上げ受給した場合、65歳になるまでは遺族厚生年金などと併給することができません。いずれかの年金を選択する必要があります。
また、繰り上げ受給すると寡婦年金や事後重症(後から重症化したケース)などによる障害年金を受け取れなくなります。
このように他の年金との兼ね合いがあるため、老齢年金以外の年金を受け取れる人や受け取れる可能性のある人は、より慎重な検討が必要と言えます。
公的年金を繰り下げ受給するメリット
続いて、公的年金を繰り下げ受給する(受け取り開始を遅くする)メリットについて見ていきましょう。
1年間遅く年金の受け取りを開始すると年金額が8.4%増える
繰り下げ受給にすると、1回当たりの年金額が増額されます。
増額率は1ヶ月当たり0.7%で、1年遅らせて66歳から受給し始める場合は8.4%増える計算です。最大で75歳まで遅らせることができますが、その場合は年金額が84%増えます。
増額された年金額は、一生涯ずっとそのままです。 また、繰り上げ受給するケースと異なり、繰り下げ受給する場合は国民年金と厚生年金の一方のみを繰り下げ受給することもできます。
長生きするほど受け取れる年金の総額が多くなる
老齢年金は、長生きするほど受け取れる年金の総額が多くなります。特に繰り下げ受給の場合、長生きすればするほど、増額された年金を受け取り続ける期間が長くなります。
80歳、90歳と長生きした場合には、通常の受け取り方(65歳開始)や繰り上げ受給よりも繰り下げ受給を選んだ方が総額が多くなる可能性が高いでしょう。
収支のマイナス分が減ることで老後資金が長持ちする
老後資金として1,000万円準備している人の場合、仮に収入よりも支出の方が毎月5万円多い赤字状態が続くと、16~17年で資産が底を付きます。しかし、繰り下げ受給によって年金が増額された状態で、月3万円のマイナスに抑えられれば、30年近く長持ちさせることができます。
老後に収入が減って資産の取り崩しが必要となるケースは珍しくありません。準備した老後資金をできる限り長持ちさせるためには、年金を含む収入を増やすなどの工夫が大切です。
公的年金を繰り下げ受給する場合の注意点
繰り下げ受給にも注意点があります。メリットだけではなく、注意点もよく確認しておきましょう。
加給年金を受け取る権利を失う可能性がある
厚生年金に20年以上加入して年金を受け取っている人が、65歳になった時点で、64歳未満の配偶者や18歳未満の子どもの生計を維持している場合は「加給年金」の対象になります。
配偶者や子ども数に応じて年金額が加算される制度ですが、例えば夫(厚生年金の被保険者)より妻が年下で、夫が繰り下げ期間中に、妻が65歳の誕生日を迎えた場合、64歳未満の配偶者という条件を満たさなくなるため、加給年金を受け取る権利を失います。また、加給年金の部分は繰り下げ受給しても増額されません。
社会保険料と税金の負担が増加する
老齢年金には税金や社会保険料がかかります。給与収入と同じように、収入が多くなるほど税金や社会保険料も高くなるので注意が必要です。
健康保険の高額療養費など、収入が多いと負担が増える仕組みになっている制度もあります。また、老後も働き続けている場合は、前述の在職老齢年金(年金+給与収入の金額が一定以上だと年金が支給停止される制度)も意識しておきたいところです。
資産寿命を延ばす方法

老後にお金が尽きることを心配している人もいるでしょう。お金の不安がない状態で長く安定した生活を送るには、資産寿命を延ばすことが肝心です。
最後に、どうすれば資産寿命を延ばせるのか、その方法を紹介します。
繰り下げ受給を選択し、月々の年金収入を増やす
65歳以降も収入が見込める人やまとまった資産があるなど、比較的お金に余裕がある人は、繰り下げ受給を検討するのがおすすめです。
繰り下げ受給を選択して75歳まで受給開始を遅らせると、年金額を84%増額できます。75歳まで待てない場合でも、受給開始時期は1ヶ月単位で選択できます。収入が減るタイミングなどに合わせて、なるべく遅く受け取り始めると良いでしょう。
取り崩しながら資産運用を続ける
これまで貯めた資産を取り崩す時期がきても、資産運用を完全にやめるのではなく、資産運用を続けながら、資産を取り崩すのがおすすめです。
なお、老後は資産運用を続けられる期間が若い頃に比べて短くなるので、リスクを抑えながら資産運用をしていくことが望ましいと考えられています。
資産運用を続けながら取り崩すことで、資産運用をせずに取り崩す場合と比べ資産寿命を延ばすことが期待できます。
資産運用は運用益が非課税となるNISA(少額投資非課税制度)を活用すると良いでしょう。大きなリターンを狙った資産運用ではなく、資産を守っていくための資産運用を続けることが大切です。
公的年金の繰り下げ受給と資産運用で資産寿命を延ばそう

老後の公的年金の受け取り方は「原則通り65歳から」「繰り上げ受給」「繰り下げ受給」の3種類に大別されます。
お金の不安なく長生きすることを考えるなら、年金は働けなくなった時のセーフティーネットと考え、繰り下げ受給を選択し、老後も資産運用を続けて、資産寿命を延ばすのがおすすめです。
「資産運用に興味がある」
「自分に合った運用方法を教えてほしい」
という人は、ウェルスナビの無料診断を利用してみましょう。
最短1分であなたに合った資産運用プランを提案します。