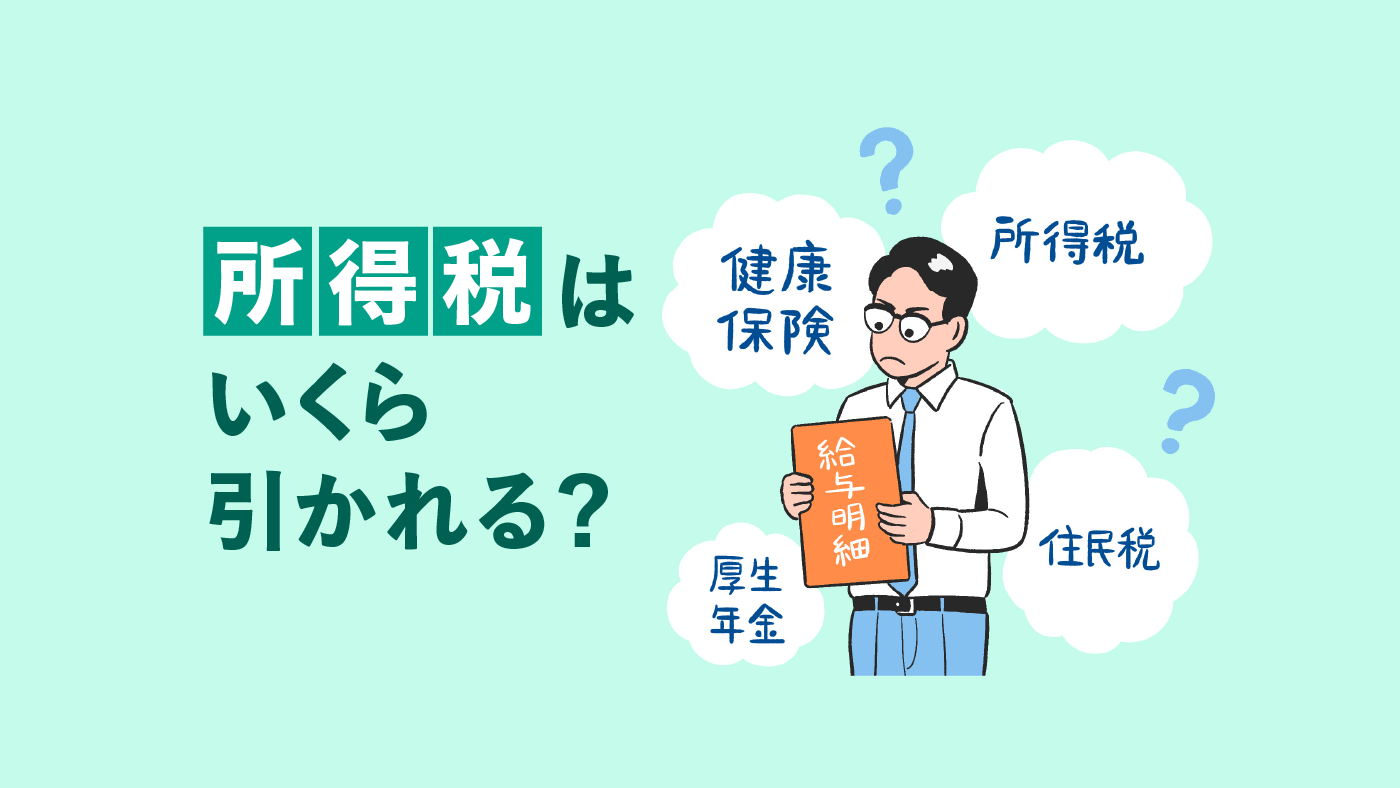お金のことで漠然とした不安や悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。それを解決するには、家計を上手に管理できるようになるのが近道です。
この記事では、お金に関する不安をなくし、豊かな人生を実現するために欠かせない、家計管理の考え方とやり方について解説します。
目次
- 多くの人がお金に関する不安を抱えている
- 家計管理は豊かな人生を実現するための第一歩
- 家計管理は、短期と中長期に分けて考える
- まずは現状の収入や支出を把握する
- 収支を黒字化し、生活予備資金を確保する
- 中長期的な視点で家計管理を考える
- 人生3大資金の準備をする
- 支出を減らし、収入を増やしてお金を貯める
- お金が貯まりやすくなる2つのコツ
- まとめ
多くの人がお金に関する不安を抱えている

日本FP協会が2023年に行った調査(※1)によると、仕事をしている20~30代の人のうち「将来のお金に対する不安がある」と答えた人は全体の8割以上にのぼりました。
子ども1人あたりの教育費として1,000万円、住宅購入に4,000万円、老後に2,000万円不足など、巷で必要といわれる金額はあまりに大きいものです。準備できるという自信を持てずに、頭を抱えてしまうこともあるでしょう。
また、不安を解消するために対策したいと思っていても、「お金の話は難しくて苦手」「やり方がわからない」などさまざまな理由で、うまくできずに悩んでいる人も少なくありません。
※1 日本FP協会「これからのお金と給料に関する意識調査」(2023年11月24日)
家計管理は豊かな人生を実現するための第一歩

お金の不安を軽減し、豊かな人生を実現するために重要なのが「家計管理」です。
現在と未来の収支を把握してうまくコントロールすることができれば、充分な貯蓄を用意できる可能性が高まります。そして、突発的な出費への対応はもちろん、理想の暮らしを実現させることもできるでしょう。
では、家計管理はどうすれば上手にできるのでしょうか。
家計管理は、短期と中長期に分けて考える

家計管理は難しそう、なかなかお金が貯められない……と感じている人もいるでしょう。そんなときは、短期的な目標と中長期的な目標を分けて考えるとよいでしょう。
ひとくちに家計管理といっても、今日1日、今月1カ月分といった短期的なやりくりを指す場合もあれば、数年、数十年先の未来まで見据えて計画的にお金を貯めていくことを指す場合もあります。
これらすべてに一気に取り掛かろうとすると、あまりにハードすぎて挫折してしまうかもしれません。一見遠回りに思えても、1つずつ分解して、順番に取り掛かっていくのがおすすめです。
まずは現状の収入や支出を把握する

上述のとおり、家計管理には順番があります。まず考えるべきなのは短期的な目標の達成です。
目の前の数字を把握する
家計管理の第一歩として、まずは現状の収入や支出などを把握することから始めましょう。
【確認すべきポイント】
・年収や毎月の手取り額はいくらか?
・今、何に、いくら使っているか?
・3年以内に必要になるお金(教育資金、住宅購入の初期費用、自動車の購入・買換え費用、引越し費用など)はいくらか?
収入は給与明細を見ればすぐにわかりますが、支出はなかなか把握しにくいかもしれません。家計簿を付けるのがおすすめですが、より手軽に済ませたいなら買物のレシート、通帳やクレジットカードの明細、領収書などを確認するだけでも効果があります。
短期間で達成できる目標を立てる
続いては、家計を今後どうしたいのか考えて、目標を立てることです。目標設定のコツは、1年以内に達成可能な内容にすることです。たとえば「収支を黒字化させる」「3カ月分の生活費程度の貯蓄を確保する」などです。
難しすぎず短期間で達成できる目標なら、ハードルが低いため始めやすいでしょう。さらに、比較的かんたんに「達成した」という成功体験を得られるため、モチベーションを維持しやすくなります。
収支を黒字化し、生活予備資金を確保する

家計管理において、まず達成したい短期目標が3つあります。まだ達成できていない場合は、目標に据えて重点的に取り組んでみましょう。
支出を見直して収支を黒字化させる
毎月の収支が赤字(収入<支出)になっている人は、できるだけ早く黒字(収入>支出)にできるようにしましょう。黒字化に向けて必要不可欠なのが支出の見直しです。
【支出の見直しのポイント】
・まずは金額の大きな支出から見直しを始める
・固定費(毎月一定額の支出が継続する支出)を見直す
・自分が価値を感じるものだけにお金を使う
やみくもに何でも支出を減らそうとすると、我慢ばかりでつらくなってしまいます。優先順位を決めて、お金を使うところと使わないところのメリハリをつけましょう。
生活予備資金を確保する
収支が黒字になったら、次は「生活予備資金」の確保を目指しましょう。生活予備資金とは、最低限の生活に必要な月額費用の3〜6ヶ月分と、近い将来に使う予定がある金額を足したお金のことです。
生活予備資金は、安心して生活するために欠かせない「もしもの備え」です。生活予備資金に相当する金額が貯まっていれば、入院や休職などで突発的に収入が減った(もしくは支出が増えた)ときでも問題なく対応できるでしょう。
生活予備資金との差額を投資に充てる
生活予備資金が確保できたら、その後の貯金分は投資に充てて、より効率的にお金を増やせるようにしましょう。
生活予備資金は数百万円程度の場合が多いですが、将来のために準備すべき資金は数千万円~1億円程度と大きな差があります。この差を埋めるためには、余裕資金を長期的な投資に充ててお金を増やす仕組みを構築することが大切です。
投資とは、たとえば株式や債券といった金融資産への投資もあれば、自分の収入アップを目的とした自己投資もあるでしょう。いずれにしても投資は少しずつコツコツと長期的に取り組んでいくのがおすすめです。
中長期的な視点で家計管理を考える

短期目標を達成できたら、次は中長期的な視点で家計管理を考えてみましょう。そのための準備として必要なことを2つ紹介します。
将来どうしたいかを具体的にイメージする
自分や家族にとって理想の暮らしとはどんなものか、将来いつどんなことをしたいのか、未来をイメージしてライフプランを立ててみましょう。
【イメージしておきたい項目】
・何歳まで働くか?
・子どもにはどのような教育を受けさせたいか?
・将来はどんな生活が理想か(毎年海外旅行に行きたい、田舎でのんびり…など)?
・理想の暮らしを実現するにはいくら必要か?
・今のまま行くとリタイア予定時期にいくら貯まっているか?
・100歳まで生きたら、いくら老後資金が不足するか?
など
実現したい未来によって必要な金額が大きく変わってくるため、できる限り具体的に考えるのがポイントです。
ライフイベントごとに必要なお金ともらえるお金を調べる
結婚、出産、引越し、転職、退職など、家計に影響するライフイベントはいくつもあります。ライフイベントごとに、必要なお金と受け取れるお金について調べてみましょう。
特に、住宅資金・教育資金・老後資金の3つは、人生の中でも突出して高額な出費になりやすいことから「人生3大資金」と呼ばれています。
それぞれいくら必要で、いくらもらえて、いくら足りないのか具体的に確認しておくと、不安の解消や有効な対策につながります。
人生3大資金の準備をする

住宅資金・教育資金・老後資金のいずれにも言えることですが、いきなり「30年後に迎える老後に向けて2,000万円を貯める」など遠い目標を立てると挫折しやすくなります。着実に目標を達成し、お金の不安を軽減させるために押さえておきたい重要なポイントを紹介します。
住宅ローンや家賃は無理なく払える金額を意識する
住宅資金全体を見ると数千万円と高額ですが、まずは、住宅購入のための初期費用として物件価格の10~20%程度を目標に貯めると良いでしょう。
住宅購入の初期費用には、頭金と諸費用がありますが、最近では、頭金なしで物件価格の全額を借りられるケースも増えています。ただし、住宅ローンを借りすぎると住宅ローン破綻などのリスクが高まります。住宅ローンを組んで家を購入する場合は、借りられる金額ではなく、無理なく返済できる金額を目安に借りることが大切です。
一方で、家の購入申し込みにかかる初期費用や手数料、税金などの諸費用は原則住宅購入時点で支払わなければいけません。金額の目安は住宅価格の3~9%程度になるため、住宅の購入申込をするまでの期間で、計画的に資金を準備しておきましょう。
もし、数年後に住宅購入を検討しているのであれば、高いリスクを伴う運用方法は向きません。できる限りリスクを抑えた方法で貯める計画を立てましょう。
また、住居費は家計の中で大きな割合を占める固定費です。無理をして身の丈に合わない家に住むと、家計が圧迫されて生活が苦しくなってしまいます。
賃貸の場合は、火災保険料や更新料、駐車場代などの費用が継続してかかることを想定しながら、余裕を持って支払える家賃の物件を選びましょう。
教育資金は安全性と収益性のバランスを考えて貯める
教育資金とは、子どもの学費や塾代、習い事代などです。使う時期や金額がおおむね決まっているという特徴があるため、安全性と確実性を重視して貯めていく必要性があります。
たとえば幼稚園から大学まですべて公立の場合、学費の総額は平均で約800万円です。単純に計算すると、年間40~50万円、1カ月あたり3~4万円の負担になります。
子どもが生まれたら児童手当を貯金に回すなど、早いうちから計画的に貯めていきたいところです。
ただし、教育資金で特に大きな割合を占めるのが大学の学費で、教育資金の負担が家計を圧迫しやすいのも子どもが大学在学中のタイミングです。子どもが生まれてから大学進学までは、約18年の時間がありますので中期的な運用も可能です。
教育資金は、安全性を重視して堅実に積み立てる部分と、収益性を意識して中長期的に運用する部分をバランス良く組み合わせて準備するのがおすすめです。
ライフプランとセットで老後のお金について考える
老後資金が不足することを心配している人も多いかもしれませんが、老後資金は人生3大資金の中で最も準備に時間をかけることができる資金です。20年、30年…と時間をかけて運用していくことで、無理なく準備できる可能性は十分にあるでしょう。
また、老後に必要な金額は、人によって大きく異なります。5,000万円準備しても足りない人もいれば、数百万円程度で足りる人もいるでしょう。将来受け取れる年金や退職金の金額も個人差が大きいので、一度調べてみるのがおすすめです。
自分の場合はいくら準備しておけば良いのか、前述のライフプランも踏まえて具体的に計算してみましょう。
支出を減らし、収入を増やしてお金を貯める

「毎月貯めるお金って増やせるの?」という疑問を持っている人もいるでしょう。貯めるべき時に節約して貯めることと、収入を上げるための取り組みができれば、十分可能です。
一般的に、人生の中で特にお金を貯めやすい時期(貯めどき)は独身時代・出産前・定年直前と言われています。貯めどきには通常より積極的に貯めるような計画を立てるのがおすすめです。
目先の問題が解決して、貯めるべき金額がわかったら、より長期的な目標を立てると良いでしょう。仕事や運用など、収入アップのために何ができるか考えて実行することも有効です。
お金が貯まりやすくなる2つのコツ

最後に、家計管理の中長期目標の達成確率を上げるために知っておきたい、お金が貯まりやすくなるコツを紹介します。
口座を目的ごとに分けて管理する
家計管理をするときは、普段使う預金口座とは別に、貯蓄用の口座を作っておくのがおすすめです。
「使っても大丈夫なお金」を「手を付けてはいけないお金」と明確に区別しておくことができ、さらに、じわじわと貯金が増えていく様子がわかりやすいためモチベーションの維持にも役立ちます。
強制的に貯蓄する仕組みを作る
貯めることが苦手な人はぜひ「先取り貯蓄」を実践してみましょう。給与が入金されたらすぐに貯蓄用の口座に自動的に一定額が移動する仕組みを作っておくことで、半強制的に貯めていくことができます。
勤務先の財形貯蓄制度や銀行の定額自動入金サービスなどを利用すると、かんたんに設定できます。
まとめ
この記事のポイントは以下のとおりです。
- お金の不安を解消するには家計管理が大切
- まず目指すべきなのは「収支の黒字化」「生活予備資金の確保」
- 次に目指すべきなのが、人生3大資金に備えて中長期的に貯蓄すること
- 貯金の成功率を上げるには「口座を分ける」「先取り貯蓄」が有効
家計管理は1つずつ順番に実践していけば難しくありません。自分が今どこまで実践できているのか確認してみましょう。