「自分の貯金額は同世代と比べて多い?少ない?」「他の人はどれくらい貯めている?」と気になる人もいるでしょう。この記事では、現役世代の各年代の貯金額(預貯金残高)や貯蓄額(金融資産保有額)の平均値と中央値を紹介します。
貯蓄額(金融資産保有額)には、預貯金だけでなく株や投資信託、貯蓄型の保険などの資産が含まれています。また、中央値は平均値のように飛び抜けて大きい数値に引っ張られて変動することがないため、より実態に近い数値と言われています。それぞれをチェックして、自分の資産状況と比較してみましょう。
併せて、貯蓄を増やすコツについても解説します。将来に向けた資産形成にぜひお役立て下さい。
【年代別】平均貯蓄額はいくら?
日本銀行が事務局を務める金融広報中央委員会が行った「家計の金融行動に関する世論調査」をもとに、各世代の預貯金残高と金融資産保有額の平均値・中央値を見ていきましょう。

上の表の通り、年代が上がるほど、預貯金残高も金融資産保有額も上がる傾向が見られます。
ここでいう「預貯金残高」とは、普通預金や定期預金などのうち、運用または将来の備えのために蓄えている金額を指します。なお、「金融資産保有額」には預貯金残高に加えて株・投資信託などの資産も含まれますが、不動産や金などの実物資産は含まれません。
金融資産保有額は「中央値」が公表されています。中央値は平均値より実態に近い数値とされており、正しく実態を把握するためにぜひ確認しておきたいポイントです。
【20代の平均的な貯蓄事情】
各年代ごとのデータを詳しく見ていきましょう。まずは、20代の平均的な貯蓄事情を紹介します。
20代の平均預貯金残高は75万円
20代の預貯金残高の平均は75万円、金融資産を保有していない世帯を含めた金融資産保有額の平均は151万円でした。金融資産保有額の中央値は10万円となっています。
20代は他の年代に比べて資産が少ない傾向が見られます。これは、20代はまだ若く、収入が少ない人や社会人になったばかりの人も多いことが要因の1つと推察されます。
20代世帯の42.2%は金融資産を保有していない
20代では、金融資産を保有していない世帯の割合は42.2%にのぼります。
同調査によれば、20代でも9割以上の人が金融機関の口座を持っています。しかし、預貯金残高があっても日常の出し入れや引き落としのためのお金しかない(運用や将来の備えのためのお金ではない)人も多いようです。
20代単身世帯は手取りの18%を貯蓄している
20代単身世帯のうち、金融資産を保有していると回答した世帯に限って見てみると、手取り収入のうち平均18%を貯蓄に回しているという結果が出ています。
金融資産保有額は他の世代に比べて少ない20代ですが、実は手取りから貯蓄に回している割合は他の世代より高いという特徴があります。特に、家族を養う必要がなく身軽な単身世帯ではその傾向が顕著です。
20代二人以上世帯は手取りの14%を貯蓄している
上記と同じく世帯主が20代の二人以上世帯のうち、金融資産を保有していると回答した世帯に限って見てみると、手取り収入のうち平均14%を貯蓄に回しています。
二人以上世帯の貯蓄割合は、単身世帯より低いです。しかし、金融資産保有額の平均値や中央値は単身世帯を上回っています。
20代では半数近く人が収益性重視で金融商品を選んでいる
20代で金融資産を保有している世帯では、金融商品の選択において「安全性」や「流動性」よりも「収益性」を重視している人が多いという結果も出ています。
収益性を重視している人は単身世帯では46.1%、二人以上世帯では49.1%でした。この割合は若い世代では高く、年代が上がるにつれて低くなっていく傾向があります。
【30代の平均的な貯蓄事情】
続いて、30代の平均的な貯蓄事情についても見ていきましょう。データを読み解くと、20代とは違った傾向が見えてきます。
30代の平均預貯金残高は287万円
30代の預貯金残高の平均は287万円でした。金融資産を保有していない世帯を含めた金融資産保有額の平均は599万円となっています。一方で、金融資産保有額の中央値は130万円でした。
平均値と中央値の差が大きいということは、それだけ金融資産を保有している人としていない人の差が大きい、つまり多額の資産を持つ人と全く資産を持たない人がいてニ極化しているということを意味します。
30代世帯の30.2%は金融資産を保有していない
30代で金融資産を保有していない世帯の割合は、30.2%です。なお、この割合は40代・50代でもほぼ同じです。
20代の42.2%と比較すると大幅に下がっていると言えますが、それでも約3割は将来の備えや運用のための貯蓄が全くない状態です。金融資産を持たない世帯の割合は、二人以上世帯より単身世帯の方が高い傾向にあります。
30代単身世帯は手取りの17%を貯蓄している
30代単身世帯のうち、金融資産を保有していると回答した世帯に限って見てみると、手取り収入のうち平均17%を貯蓄しています。
なお、最も回答が多かったのは「貯蓄割合10~15%未満(18.7%)」でしたが、「30~35%未満(14.5%)」「35%以上(15.0%)」と答えた人も多くいました。手取りの30%以上を貯蓄に回す人の割合は合計で約30%と、全年代で最も高くなっています。
30代二人以上世帯は手取りの14%を貯蓄している
上記と同じく世帯主が30代の二人以上世帯のうち、金融資産を保有していると回答した世帯に限って見てみると、手取り収入から貯蓄に回す割合は平均14%となっています。
前述の20代と同様、貯蓄に回す割合は二人以上世帯の方が低いですが、金融資産保有額の平均値や中央値は単身世帯を上回っています。
30代の人も収益性重視で金融商品を選んでいる傾向が強い
20代に続き30代でも、金融商品を選ぶ際に「安全性」や「流動性」より「収益性」を重視する傾向が見られました。
30代で金融資産を保有している世帯では、金融商品の選択基準として収益性を重視している人が、単身世帯では49.1%、二人以上世帯では44.4%と最も多くなっています。
【40代の平均的な貯蓄事情】
続いては40代です。30代より資産額が多くなる一方で、単身世帯と二人以上世帯の差が開いていく世代でもあります。データをもとに40代の平均的な貯蓄事情を見ていきましょう。
40代の平均預貯金残高は340万円
40代の預貯金残高の平均は340万円、金融資産を保有していない世帯を含んだ金融資産保有額の平均は811万円でした。
金融資産保有額の中央値は180万円ですが、単身世帯では47万円、二人以上世帯では220万円とかなり差があります。平均値と中央値の乖離も30代より大きく、40代は貯蓄額の個人差がより大きくなってくる年代と言えます。
40代世帯の30%は金融資産を保有していない
40代で金融資産を保有していない世帯の割合は30.0%と、前述の30代とほぼ同じです。ただ、単身世帯に限って見ると40.4%にのぼり、30代や50代の単身世帯よりも高くなっています。
40代では金融資産保有額が0~200万円未満の世帯が約50%を占めていて、貯蓄が難しい人も多いと見られます。
40代単身世帯は手取りの14%を貯蓄している
40代単身世帯のうち、金融資産を保有していると回答した世帯に限って見てみると、手取り収入のうち平均14%を貯蓄に回しています。
一般的には30代より40代の方が収入が多い傾向があります。しかし、貯蓄に回す割合は30代(平均17%)よりも低い結果となりました。
40代二人以上世帯は手取りの12%を貯蓄している
同じく世帯主が40代の二人以上世帯のうち、金融資産を保有していると回答した世帯に限って見てみると、手取り収入のうち平均12%を貯蓄に回していることが分かります。
単身世帯同様、20代や30代よりも貯蓄に回す割合が低くなっています。40代の二人以上世帯では、子育てにお金がかかって家計が圧迫され、貯蓄が難しくなっている人もいると推察されます。
40代の人も収益性重視で金融商品を選んでいる傾向が依然として強い
20代・30代に続き40代でも、金融商品を選ぶ際に収益性を重視している人が多い傾向が見られました。
利回りや将来の値上がりなど、収益性を選択基準とする人は単身世帯では43%、二人以上世帯では41.4%と、20代、30代よりは割合が低くなっているものの、依然として高い割合です。
【50代の平均的な貯蓄事情】
続いて、50代の平均的な貯蓄事情も見ていきましょう。
50代の平均預貯金残高は482万円
50代の預貯金残高の平均は482万円でした。金融資産を保有していない世帯を含めた金融資産保有額の平均は1,212万円、中央値は200万円となっています。
これまで見てきた年代の中で最も平均値と中央値の差が大きく、貯めている人と貯めていない人の差が開いていることが分かります。
50代世帯の30.3%は金融資産を保有していない
50代で金融資産を保有していない世帯は30.3%と、30代・40代と同程度の割合でした。
しかし、貯蓄がない人が3割いる一方で、金融資産を保有している世帯に限って見ると、最も回答が多かったのは「金融資産保有額3,000万円以上(15.4%)」でした。
この結果からも、たくさん貯めている人と全く貯めていない人とで二極化が進んでいることが分かります。
50代単身世帯は手取りの14%を貯蓄している
50代単身世帯のうち、金融資産を保有していると回答した世帯に限って見てみると、手取り収入のうち平均14%を貯蓄に回しています。
この数値だけ見ると40代と同じですが、実は50代では「5%未満」「5~10%未満」「10~15%未満」と答えた人の割合が40代より高くなっています。
ただ「25~30%未満」と答えた割合も高く、なかなか貯蓄ができない人と余裕を持って貯蓄を進めている人が混在していることがうかがえます。
50代二人以上世帯は手取りの12%を貯蓄している
世帯主が50代の二人以上世帯のうち、金融資産を保有していると回答した世帯に限って見てみると、手取り収入のうち平均12%を貯蓄しているという結果が出ています。単身世帯だけでなく二人以上世帯でも、40代と同じ割合になりました。
全年代を通して、二人以上世帯は単身世帯より金融資産保有額が多い傾向があります。しかし唯一、50代の平均値だけは二人以上世帯が1,147万円、単身世帯が1,391万円と逆転します。
50代以上は二人以上世帯の人を中心に安全性重視で金融商品を選ぶ傾向が高まる
金融資産を保有している世帯では、50代でも単身の場合は「収益性」を重視して金融商品を選ぶ人が41.6%と依然として高い割合になっています。
しかし同じ50代でも、二人以上世帯では「安全性」と回答する人が28.9%と増え始めます。本記事では詳しく紹介していませんが、その後60代・70代と年代が高くなるにつれて、安全性を重視する傾向がより強まっていきます。
平均貯蓄額のデータから読み取れることは?
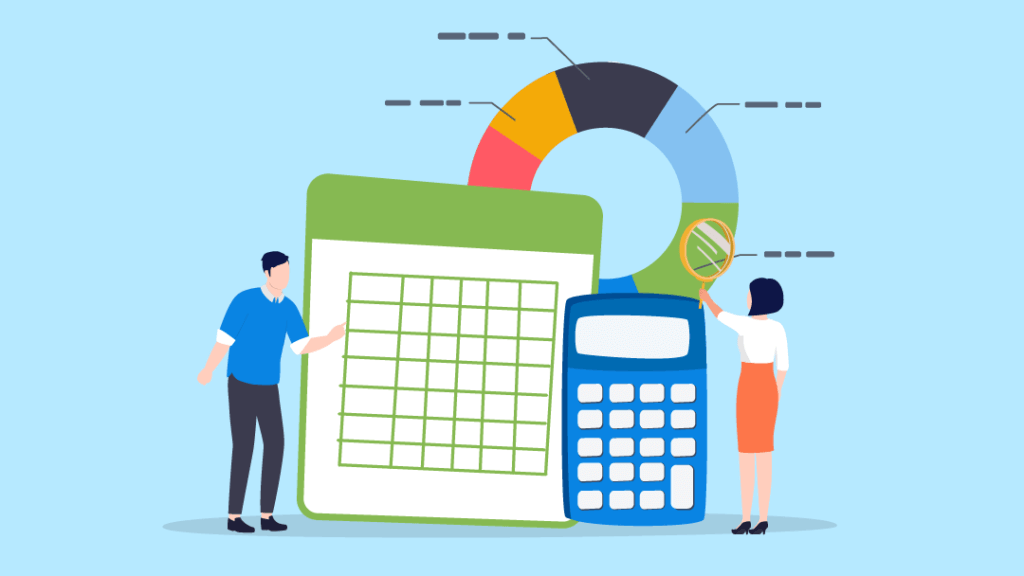
ここまでに紹介したデータから読み取れる内容を、かんたんに整理しておきましょう。おもなポイントは次の3点です。
貯蓄ができる人と全くできない人の差が大きい
貯蓄ができる人と全くできない人、両者の差がとても大きいです。そのため、飛び抜けて高い数値に引っ張られやすい「平均値」と、実態に近い「中央値」がかけ離れている点に注意が必要です。
貯蓄できている世帯は、手取り収入の1割以上を継続して貯蓄に回しています。一方で、どの世代でも金融資産を持っていない世帯が30~40%にのぼっています。貯めている人とそうでない人の差が激しく、二極化している傾向が見られます。
若い世代の方が貯蓄割合が高い傾向にある
若い世代は給与が少ない傾向があり、貯蓄に不利と思われがちです。しかし、データを読み解くと、若い世代の方が貯蓄割合(手取り収入のうち貯蓄に回している割合)が高いことが分かります。
特に、20~30代の単身世帯は貯蓄割合が高い傾向があります。
金融資産を持つ世帯は、収益性重視で金融商品を選ぶ傾向が強い
金融資産を持っている世帯では「収益性」を重視して金融商品を選ぶ傾向が見られました。年代を問わず、金融資産を持っていない世帯より持っている世帯の方が、収益性を重視する人の割合が高くなっています。
年代が上がるにつれて安定性を重視する傾向が強まるものの、20代~50代ではいずれも収益性を重視する人の割合が最も高いという結果でした。
人生3大資金から逆算して貯蓄額の目標を立てよう

貯蓄をするなら、やみくもに行うのではなく、明確な目的を持って行うことが大切です。何のためにいつまでにいくら必要なのか考え、そこから逆算して貯蓄の目標額を設定するようにしましょう。
特に、人生の中でも多額のお金がかかるとされる3大資金(住宅資金、教育資金、老後資金)を意識して目標を立てるのがおすすめです。
住宅購入資金は物件価格の10~20%を目標に貯める
将来的にマイホームの購入を希望している場合は、まず頭金や諸費用などに充てる初期費用分を目標にして貯蓄を進めると良いでしょう。具体的には、購入したい物件の価格の10~20%が目安です。
なお、住宅ローンの返済額を手取り収入の25%程度までに抑えておくと、家計のやりくりがしやすいと言われています。無理のない範囲で計画的にローンを組みましょう。
教育資金は安全性と収益性のバランスを考えて貯める
子ども1人当たりの教育資金は1,000万~2,000万円近くになると言われています。特に、大学進学時には多額の出費が予想されます。
ただ、教育資金はお金が必要になる時期がある程度はっきりしていて、中長期で準備できるという特徴があります。貯蓄や保険といった安全性重視の手段だけでなく、運用なども併せて検討するのがおすすめです。
運用は、時間をかければかけるほど複利の効果(利益が新たな利益を生むことで、どんどんお金が増えやすくなっていく効果)が期待できます。
ライフプランとセットで必要な老後資金を考える
老後資金としていくら必要なのかは、思い描くライフプランによって大きく異なります。
受け取れる年金や退職金の金額を確認しておくことも重要ですが、何歳まで働きたいのか、どんな老後生活が理想なのか、ライフプランとセットで考えてみると良いでしょう。なるべく具体的な数字で計算してみるのがポイントです。
貯蓄できる人が実践している!お金が貯まる家計にする方法

最後に、貯蓄できる人になるためには何を意識すれば良いのか確認しておきましょう。3つのポイントについて解説します。
金額が大きい固定費から支出を見直す
「もっと貯蓄できる家計を目指して、出費を見直してみよう」と思うこともあるでしょう。
そんな時は、食費や交際費などの変動費(支払い額が毎月変わる出費)からではなく、住居費や保険料など金額が大きい固定費(支払い額が毎月一定の出費)から見直すのがおすすめです。
金額が大きい固定費は、見直しに成功した場合の節約効果が大きく、しかもその効果が長く続きやすいという特長があります。
口座を目的ごとに分けて管理する
普段使う預金口座とは別に、貯蓄用の口座を作って管理するのも良い方法です。各口座をうまく使って、お金の色分け(区別)をしておきましょう。
「長女の進学費用」「5年後の住宅購入資金」など具体的な目的ごとに口座を分けておけば、進捗状況を把握しやすく、誤って手を付けてしまう事態も防げます。
強制的に貯蓄する仕組みを作る
貯蓄が苦手な人でも「強制的に貯まる仕組み」さえ作っておけば貯めやすくなります。
強制的に貯まる仕組みとは、例えば給料が入金された直後に貯蓄用の口座に自動的にお金が移動する仕組みのことで「先取り貯蓄」とも呼ばれています。
具体的には、勤務先の財形貯蓄制度や、銀行の定額自動入金サービスのほか、家計の状況次第ではNISAの積立設定の利用もおすすめです。定期預金や投資用口座など入金先を気軽にお金を引き出しにくい口座に設定しておくことで、貯蓄の成功率がより高まるでしょう。
まとめ 人生3大資金を中長期的な貯蓄で備えよう
この記事では、年代ごとの預貯金残高と金融資産保有額を紹介しました。単に多い・少ないと一喜一憂するだけではなく、今後に向けて適切な目標設定を行い、貯蓄できる人が実践しているポイントを押さえて、上手にお金を貯められる人になりましょう。
人生3大資金(住宅資金・教育資金・老後資金)のための貯蓄は特に重要です。預貯金以外の方法で貯めるのも有効ですが、万が一の際に生活を維持するために必要な生活予備資金分の預貯金を確保するまでは、無理して投資する必要はありません。
生活予備資金の目安は「最低限の生活に必要なお金」の3~6ヶ月分と、「近い将来使う予定のあるお金」を足した金額です。まずは生活予備資金を蓄えてから、次の行動を考えましょう。
「もしもの時の備えについて考えたい」
「どんな時にいくら必要になるか詳しく知りたい」
「保険を使った貯蓄方法に興味がある」
という人は、下記の無料相談をお試し下さい。
「生活予備資金分の預貯金はある」
「自分に合った運用方法が分からない」
という人には、最短1分で結果が分かる下記の診断が便利です。





