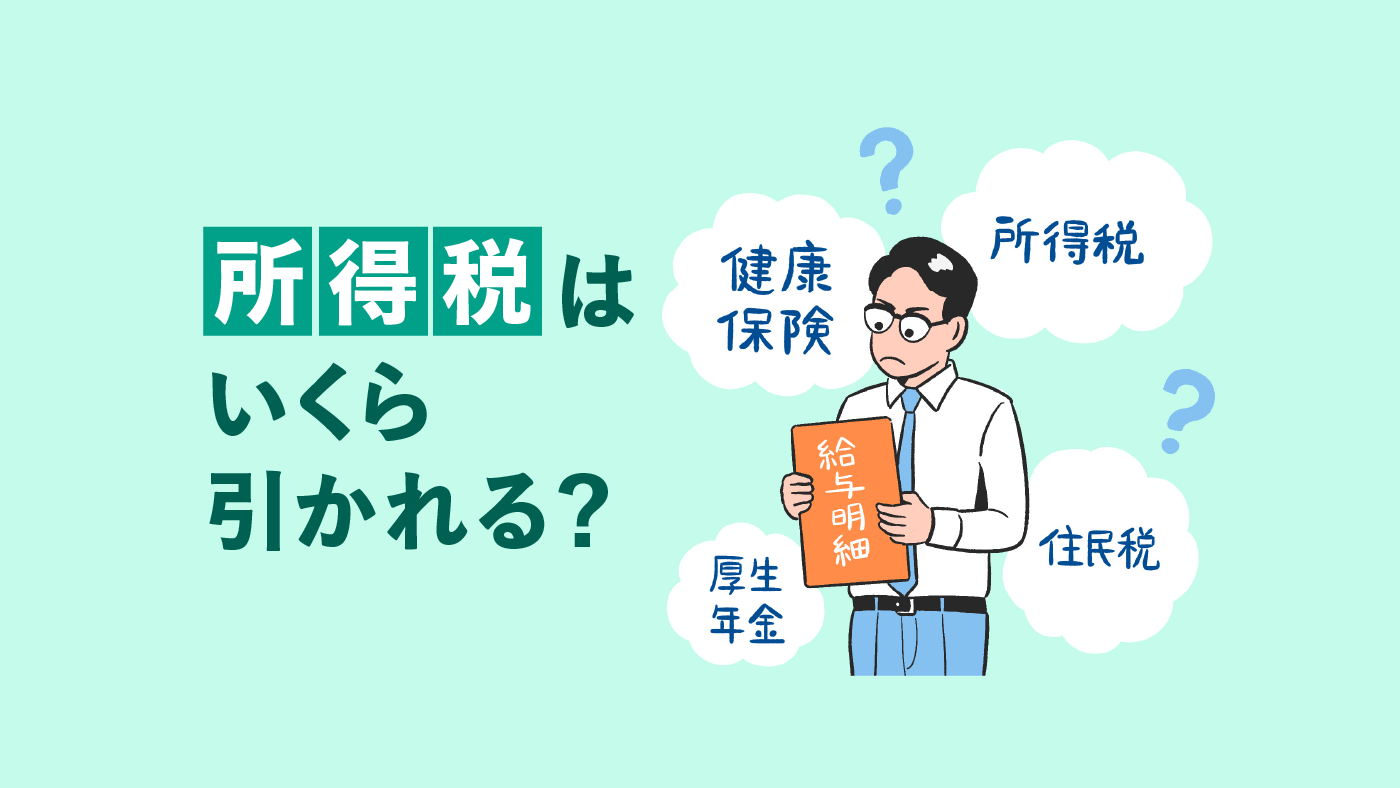家計管理においてまず確保すべきは「生活予備資金」ですが、その他にも「人生3大資金」という中長期的に準備しておくべきお金があります。
今回は「人生3大資金」が、いつ、どれくらいのお金が必要になるのかを解説します。この記事を参考に、中長期的な貯蓄目標を考えてみてください。
目次
- 「人生3大資金」は計画的に準備する
- 大きな固定費となる住居費は、無理なく払える額で
- 教育費は子育て支援制度も活用して用意する
- 自分にとっての「老後2,000万円」を考える
「人生3大資金」は計画的に準備する

一般的に、人生3大資金とは、「住宅」「教育」「老後」にかかる費用のことを指します。いずれも多額の費用がかかるため、できるだけ早いうちから計画的に準備しておきたいところです。
お金の置き場所についても意識したい点があります。生活予備資金はすぐに引き出せるように生活用の預金口座に置いておくべきですが、人生3大資金のような大きなお金は、口座を分けて管理するのが望ましいでしょう。
大きな固定費となる住居費は、無理なく払える額で

ここからは、人生3大資金の詳細を見ていきます。まずは住宅資金からです。
実家暮らしなどの場合を除き、賃料や住宅ローンという形で住居費を毎月支払っている方が多いのではないでしょうか。ここでは主に、家賃やローンの支払いとは別で必要になる費用にどう備えるか、という観点で説明していきます。
まずは、これから住宅を購入するケースを考えてみましょう。
「人生最大の買い物」とも言われる住宅を購入する場合には、一般的に金融機関で住宅ローンを組んで住宅購入資金を調達します。最近は、物件価格の全額を借りられるケースも増えているようです。
住宅ローンは基本的に、不動産そのものの費用を支払うためのものです。一方で、住宅を購入する際には、付随するさまざまな諸費用の支払いも必要になります。
諸費用には、不動産会社に支払う仲介手数料や金融機関に支払うローン事務手数料、登記費用、火災保険料、印紙税などがあります。金額の目安は住宅価格の3〜9%程度で、たとえば3,000万円のマンションを購入するなら、諸費用の目安は90万〜270万円前後になります。
諸費用も含めた金額を借りる方法がないわけではありませんが、毎月の返済額が上がったり、破綻等のリスクや借入金利が高くなるなどのデメリットもあるため、住宅購入時点までに資金を準備しておくのが賢明です。
ちなみに住宅ローン審査において、金融機関は返済負担率(収入に占める年間の返済額の割合)の上限を年収の30〜35%程度に設定していると言われます。しかし、「借りられる額」と、「無理なく払える額」はイコールではありません。住居費は最も大きな固定費だけに、無理なく払える額は手取り年収の20%程度と考えて無理のない返済計画を立てましょう。
この考え方自体は、賃貸の場合にも当てはまりますが、購入の場合は固定資産税や修繕費など賃貸にはない費用がかかります。そのため、毎月の返済額が家賃と同程度だから大丈夫だと考えるのは危険です。
また、住宅ローンを変動金利で借りる場合、将来の金利動向によっては借り入れ金利が上昇し、返済額が増える可能性があることも頭に入れておいた方がよいでしょう。
住宅を購入した場合に発生する追加的な費用はもう1つあります。それがメンテナンス費です。長く住み続けるとどうしても経年劣化が生じます。賃貸であれば、設備の故障や雨漏りなど不具合が生じた際には、管理会社に連絡すれば原則オーナー負担で修理をしてもらえますが、マイホームの場合は自分で費用を負担しなければいけません。新築であれば、買ってすぐに修繕が発生するわけではないのでついつい忘れがちになってしまいますが、将来的に必要になる可能性を頭に入れておきたいところです。
ここまでは住宅を購入するケースを見てきましたが、「ずっと賃貸で暮らしたい」という人もいるはずです。その場合にも、毎月の賃料のほかに、火災保険料や更新料などの追加的な費用が発生する可能性があります。
たとえば更新料は貸主が自由に設定できますが、関東圏では2年毎の更新で更新料は家賃の1ヶ月分というパターンが多いようです。ご自身の賃貸契約を踏まえて計画的に準備しておくのがよいでしょう。
賃貸の良いところは、ライフスタイルの変化に柔軟に対応できる点です。一方で、高齢になると条件の良い物件を借りられなくなる可能性があるほか、家賃をずっと払い続ける必要もあります。何度も住まいを変えると、その分だけ引っ越し費用もかかります。メリットとデメリットをよく比較したうえで、自分に合った住まいを選択するようにしてください。

教育費は子育て支援制度も活用して用意する

人生3大資金の2番目は教育資金です
教育費は使う時期や金額がおおよそ決まっているため、安全性と確実性を重視して積み立てることが大切になります。必要な金額は子どもの数や教育方針などによって異なりますが、子ども一人当たりの教育費を見ると、公立と私立のどちらに通うかで金額の差が大きくなる傾向があります。
たとえば、幼稚園から大学まですべて公立を選んだ場合の費用の平均は、総額約800万円です。これだけでも「多いな」と感じた方がいるかもしれませんが、すべて私立の場合の費用は、平均でその3倍近い約2,200万円になります(※1)。
下記の表の幼稚園~高校分の費用は、学校の入学金や授業料だけでなく、通学や修学旅行、課外活動にかかる費用、教材費、塾代やスポーツなどの習い事にかかる費用などを含む教育費の総額です。ただし、大学の場合は、入学金や授業料といった大学に支払う費用のみのため、大学進学によって子どもが1人暮らしをする場合には、仕送りや家賃などが別途必要になります。

このような大きな金額を目にすると、実感が持てなかったり、途方に暮れてしまったりする人もいるかもしれません。後ほど説明する老後資金にも共通しますが、目標や計画を立てやすくするコツは、できるだけ小さな数字に分解して考えることです。
たとえば、幼稚園から大学まですべて公立の場合の費用はトータルで平均約800万円とお伝えしましたが、ざっくりと1年当たりに換算すると、年間40〜50万円ほどの負担になる計算です。それをさらに月々の支出額に分解すると3〜4万円程度になります。児童手当など公的制度を加味すると、月々の負担はさらに少なくなるでしょう。「これなら無理なく捻出できそう」と感じた人もいるのではないでしょうか。
一方で、幼稚園から大学まですべて私立の場合には、毎年平均100万円以上の支出が生じることになります。よほど収入の多い家庭でない限り、前もって進学資金を準備しておかなければ、支払いが困難になる可能性もあるでしょう。
また、あまり知られていないかもしれませんが、教育費はインフレ率(物価上昇率)も考慮して考える必要があります。というのも、過去30年間を振り返ると大学にかかる教育費は上昇傾向にあるからです。私立大学の学費は高いというイメージを持っている人は多いのですが、実は割安なイメージがある国立大学の学費はそれ以上に上昇しています。(※2)。
国立・私立大学の授業料等(授業料+入学科)の推移

これを踏まえると、教育費は今後も上昇が続くと考え、少し多めに見積もっておくのが妥当です。
全て国公立でも総額約800万円と、教育にはお金がかかりますが、そのお金を何が何でもすべて自力で用意する必要はありません。両親からの支援が期待できるかもしれないですし、公的制度(児童手当や就学支援制度)を活用する手もあります。それでも足りなければ、奨学金や教育ローンを借りるという選択肢もあるでしょう。
たとえば、子育て支援のための代表的な公的制度である児童手当は、子どもが中学校を卒業するまで給付を受けることができます(2024年2月現在)。夫婦と子ども2人で世帯主の年収が960万円程度に満たないケースであれば、子ども1人につきトータルで約200万円が支給される計算です(※3)。児童手当は子どもが0歳から給付を受けられますが、すぐに使うのではなく、将来の教育資金に充てるという選択肢もあります。
子育て支援には、国だけでなく自治体も力を入れています。活用できる制度がないか調べてみる価値はあるでしょう。
自分にとっての「老後2,000万円」を考える

人生3大資金の最後は老後資金です。2019年に社会問題化した「老後2,000万円問題」を受けて、「老後資金として2,000万円を用意しなければいけない」と思っている方は多いかもしれません。しかし、理想とする生活水準などによって、老後に必要な金額は一人ひとり異なります。
金融広報中央委員会の2022年の調査(※4)によると、年金支給時に最低準備しておくべきと考える金融資産残高は、年収が高い人ほど大きい傾向があります。
この調査では、全体の平均は1,968万円だったのに対し、年収1,200万円以上では約1.6倍の平均3,235万円でした。一方で、年収300〜500万円未満では平均1,541万円、年収300万円未満では1,295万円にとどまりました。

老後の生活費は主に年金で賄い、足りない分はそれまでに築いた金融資産を取り崩すことを想定している人が多いでしょう。しかし、平均寿命が延び、リタイア後の期間も長くなったことで、より多くの老後資金を貯める必要性が生まれています。
多額の老後資金を一気に準備することはできないため、少しずつできることから始めることが大切です。その第一歩が、毎月の収支のバランスを改善することです。
また、もし健康であるのなら、年金支給開始後もできるだけ長く働き続けることで、老後資金の取り崩しを少なくするという選択肢もあります。定年後も緩やかに仕事を続けたほうが、人生の満足度が上がる人もいるかもしれません。
老後の生活のあり方は決して一つではありません。ご自身のライフプランとセットで、老後のお金について考えてみてください。
- 文部科学省「令和3年度子供の学習費用調査」、同省「令和3年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果」、同省「2021年度学生納付金調査結果」、同省「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」
- 文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果」
- 扶養親族等が3人(児童2人と年収103万円以下の配偶者)で、世帯主の年収が960万円程度に満たないケース
- 金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査2022年」