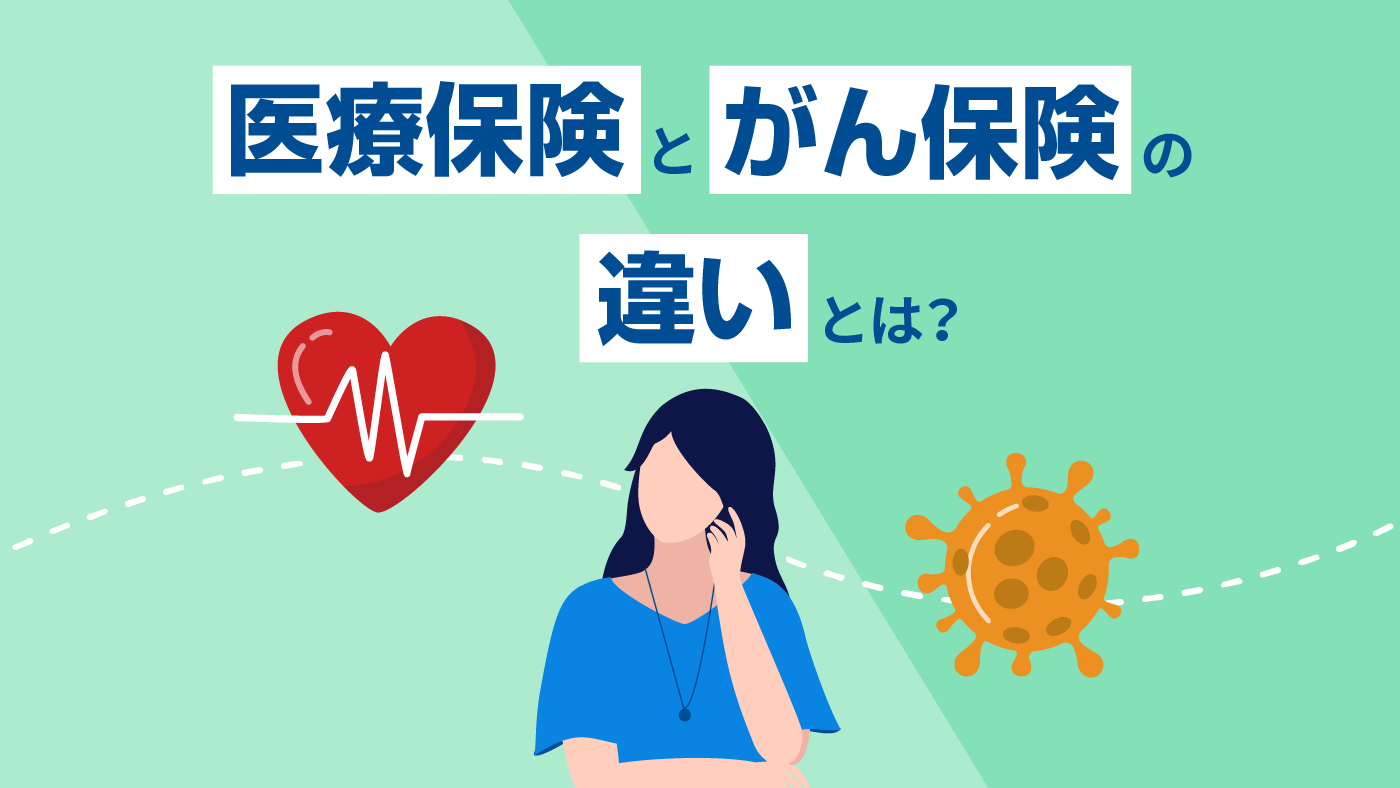医療保険やがん保険への加入を検討するなら、それぞれの特徴や違いを理解したうえで必要性を見極めることが大切です。
この記事では、医療保険・がん保険とはどのような保険なのか、どんなときにお金を受け取れるのか、どのような人に必要なのか解説します。
目次
- 医療保険とは?
- がん保険とは?
- 医療保険・がん保険選びで重要なポイントとは?
- 医療保険・がん保険はどのような人に必要な保険なのか?
- 医療保険・がん保険が自分にとって必要か考えてみよう
医療保険とは?
病気やけがに見舞われたときに役立つのが「医療保険」です。まずは、医療保険の特徴について見ていきましょう。
医療保険は入院や手術に備えるための保険
医療保険とは、病気やけがの際に医療費がかさむリスクに備えるための保険です。加入しておくと、入院や手術をしたときなどにお金を受け取れます。
どんなときにいくら受け取れるかは、加入する保険によって異なります。そのため、契約前に内容をよく確認しておく必要があります。
医療保険に加入していると主に4種類の給付金を受け取れる
医療保険で受け取れる給付金には、たとえば以下のような種類があります。
| 保険の種類 | 内容 |
|---|---|
| 災害入院給付金 | 災害や事故で入院したときに受け取れる |
| 疾病入院給付金 | 病気で入院したときに受け取れる |
| 手術給付金・放射線治療給付金 | 手術をしたとき/放射線治療を受けたときに受け取れる |
| 死亡保険金 | 亡くなったときに受け取れる |
保険会社によっては、災害入院給付金と疾病入院給付金の区別がなく「入院給付金」としている場合もあります。また、近年の医療保険には死亡保険金がついていないことが多く、ついていたとしても少額の保障のみなのが一般的です。
がん保険とは?
がんになったときは「がん保険」も役に立ちます。続いて、がん保険の特徴について見ていきましょう。
がん保険はがん治療に備えるための保険
がん保険は、がん治療に備えるための保険です。
がんの治療には高額な医療費がかかることがあります。また、仕事を休む必要が出てくるかもしれません。がん保険には、そんなときの経済的なリスクを軽減する役割があります。
医療保険との違いについては後述します。
がん保険に加入していると、主に5種類の給付金を受け取れる
がん保険の給付金には、たとえば以下のような種類があります。
| 保険の種類 | 内容 |
|---|---|
| がん入院給付金 | がんで入院したときに受け取れる |
| がん手術給付金 | がんで手術したときに受け取れる |
| がん診断給付金 | がんと診断されたときに受け取れる |
| がん死亡給付金 | がんで死亡したときに受け取れる |
| 死亡給付金 | がん以外の理由で入院したときに受け取れる |
ただ、医療保険同様、保険会社や契約プランによってどんなときにいくら受け取れるかが異なります。
近年のがん保険では、死亡保障がない代わりに「ホルモン剤治療給付金」や「外見ケア給付金」など、治療に対しての保障が充実しているものが多いです。逆に、数十年前のがん保険は、「がん=死の病」と思われていたため、死亡保障が手厚い傾向があります。
がん治療に特化している点が医療保険と異なる
がん保険は、広い意味では医療保険の一種です。ただ、さまざまな病気やけがに対応する医療保険に対し、がん保険は特定の病気だけに特化しているのが特徴です。
がんに特化している分、がんならではの事情に合わせた給付金など、医療保険にはない保障がついていることが多いです。
たとえば、がんの場合は入院も手術もせずに、通院だけで高額な治療を行うことがあります。医療保険だと対象にならないところ、がん保険だと「抗がん剤治療給付金」や「がん通院給付金」の対象になる、ということもありえます。
医療保険は「広く浅く」、がん保険は「狭く深く」備えるイメージです。
医療保険・がん保険選びで重要なポイントとは?

医療保険やがん保険を選ぶときは、以下のような点を必ず確認するようにしましょう。
- 終身か定期か
- 給付金を受け取れる条件
- 特約の内容と必要性
- 平均的な入院費用や治療の傾向
- 公的保障と企業保障
それぞれのポイントや、なぜ重要なのか解説します。
終身保険と定期保険の違いを理解しよう
保険契約上、「終身」とは一生涯ずっと保障が続くこと、「定期」とはあらかじめ期間終了の時期(満期)が決められていることを指します。
医療保険やがん保険を検討する際、終身と定期のいずれを選ぶかで、大きな違いがあります。それぞれのメリット・デメリットは以下のとおりです。
| 【終身】医療保険 | 【定期】医療保険 | |
|---|---|---|
| メリット | ・老後までずっと保障が続いて安心 ・貯蓄性がある保険もある | ・解約や見直しがしやすい ・保険料が割安な傾向がある |
| デメリット | ・保険料が割高になりがち ・解約や見直しがしにくい | ・健康状態などによっては更新できなくなる可能性がある |
ずっと加入し続ける予定なら終身がおすすめですが、「必要な時期だけ費用を抑えて加入したい」「生活環境の変化に柔軟に対応できるようにしたい」という人には定期が便利です。希望や価値観に合わせて選択しましょう。
給付金を受け取れる条件を確認しておこう
給付金の内容や金額、受け取れる条件などは、保険ごとに異なります。
たとえば同じ「入院給付金」という名称でも、「日帰り入院から対象」という場合もあれば、「○日以上の入院から対象」という場合もあります。保障が手厚い(もらえる機会や金額などが多い)ほど良いと思うかもしれませんが、その分、保険料が高くなります。
また、医療保険やがん保険では「1回の入院で○日まで」「通算○日まで」など日数の限度が決まっているのが一般的なため、加入前に確認しておきましょう。解約返戻金の有無、死亡保険金の有無なども要チェックです。
なお、がん保険には通常、加入後90日の待期期間があります。この期間中にがんと診断された場合は保障の対象にならないため、注意しましょう。
必要な特約だけセットするようにしよう
医療保険やがん保険にセットできる特約には、さまざまな種類があります。特約の有無や内容は保険会社によって異なりますが、たとえば以下のとおりです。
| 保険の種類 | 内容 |
|---|---|
| 女性特約 | 乳房や子宮、卵巣など女性特有の病気の場合のみ、保障が2倍になる |
| 三大疾病一時金特約 | がん・心疾患・脳血管疾患の場合のみ、一時金が受け取れる |
| 先進医療特約 | 先進医療を受けたときに、その技術料相当のお金を受け取れる |
| 健康祝金 | 一定期間内に保険請求がなかった場合に、祝金を受け取れる |
不安だからといって、取捨選択せずにあらゆる特約をセットしてしまうと、保険料が高額になってしまいます。
自分にはどれが必要なのか見極めましょう。「貯蓄や公的保障などでまかなえる分は保険に入らない」「本当に家計に大打撃を与えるような場合だけ加入する」など、自分の中でルールを決めておくのも有効です。
平均的な入院期間や費用、治療の傾向を調べておこう
やみくもに不安がるのではなく、実際に入院したときの費用負担や平均入院日数など、具体的な数字を知っておきましょう。場合によっては、保険に入らなくても預貯金や公的保障等でカバーできるかもしれません。
平均入院日数……32.3日
厚生労働省「令和2年度患者調査」によると、入院した人が退院するまでにかかる日数の平均は32.3日でした。ただ、がんで入院した場合のみに絞って見てみると、平均18.2日(15~34歳では10.6日、35~64歳では13.3日)と短めです。
精神疾患やアルツハイマー病など年単位の長期療養が必要になる病気もありますが、全体としては、7割近くの人が2週間以内に退院しているという結果でした。
入院時の平均費用……1日あたり約2万円
生命保険文化センターの調査では、入院1日あたりの自己負担費用は平均2万700円でした。この中には、入院にかかった治療費・食事代・差額ベッド代などに加え、交通費(見舞いに来る家族の交通費も含む)や衣類、日用品費などの出費も含まれています。
厚生労働省「令和2年医療給付実態調査」では、がんで入院した場合にかかる医療費は1入院あたり60~100万円程度(自己負担は20~50万円)となっています。
なお、近年のがん治療は入院中心から通院中心にシフトしています。従来に比べ、通院時の保障も重要になっているといえます。
公的保障と企業保障について理解を深めよう
民間の保険に加入する前に、国や自治体の「公的保障」や勤務先の「企業保障」など、すでに持っている保障について理解しておきましょう。
たとえば、仕事に関係がない病気やけがの場合は、公的医療保険(健康保険)が使えます。公的医療保険は、窓口での支払いを3割負担にする以外にも、負担を抑えるための制度(高額療養費や傷病手当金など)をいくつも兼ね備えています。
場合によっては、公的保障や企業保障がかなり手厚く、民間の医療保険やがん保険に入る必要がほとんどない人もいます。どこまで守られているかは個人差があるため、自分の場合はどうなのか確認することが大切です。
公的医療保険については、以下の記事で詳しく解説しています。
あわせて読みたい
医療保険・がん保険はどのような人に必要な保険なのか?

結局のところ、医療保険やがん保険への加入が必要な人とは、どのような人なのでしょうか。その特徴は以下のとおりです。
預貯金等が少ない人
まず、現時点で預貯金など貯蓄が少ない人は、医療保険やがん保険への加入を検討してもよいでしょう。
たとえ高額な医療費がかかっても、充分な預貯金があれば、保険なしでも乗り切れます。しかし、預貯金など緊急時にすぐに動かせるお金が少ない場合は、わずかな出費でも家計を圧迫して、家族もろとも困窮してしまうかもしれません。
具体的には、前述の入院時の平均費用程度を自力でまかなうのが難しい場合は、保険で備える必要性が高いといえます。
先進医療や自由診療を受けたいと考える人
「先進医療」や「自由診療」といった治療は、公的医療保険(健康保険)の対象になりません。そのため、全額が自己負担となり、多額の医療費がかかる可能性があります。
その他、個室に入院した場合の差額ベッド代など、高額療養費制度(医療費が高額になった場合に使える負担軽減措置)の対象にならない出費もあります。
「お金に糸目をつけずいろいろな治療法を積極的に試したい」「相部屋ではなく個室に入院したい」などこだわりがある人は、保険を使って高額な費用負担に備えておくのも1つの選択肢です。ただし、保険に加入するとそれだけ負担(コスト)が発生し、家計の圧迫にもつながります。あくまでも、保険の目的は、貯蓄や公的保険ではどうすることもできないほどの経済的なダメージをカバーするために加入するものという大前提を忘れないことが大切です。
公的保障・企業保障が少ない人
公的保障や企業保障などすでにある保障が少ない人も、保険加入を検討してもよいでしょう。
たとえば会社員や公務員の場合、病気やけがで働けなくなっても有給休暇があったり、傷病手当金を受け取れたりします。
しかし、自営業者などの場合はそれがありません。働けなくなると収入がなくなり、さらに治療費の負担が増えるため、厳しい状況に陥りやすいといえます。手薄な分を自力で補う手段として、医療保険やがん保険は有力な選択肢になるでしょう。
医療保険・がん保険が自分にとって必要か考えてみよう
病気やけがのときには「医療保険」、がんになったときには「がん保険」が役立ちます。ただ、なかには、医療保険やがん保険があまり必要でない人もいます。
加入を検討する際は、まず医療費はいくらくらいかかるのか、公的保障や企業保障、貯蓄でどれくらいカバーできているのか知ったうえで、足りない分だけを保険で補うようにするのがおすすめです。
給付金を受け取れる条件や金額などは保険会社や契約プランによって異なるため、契約前によく確認しておきましょう。