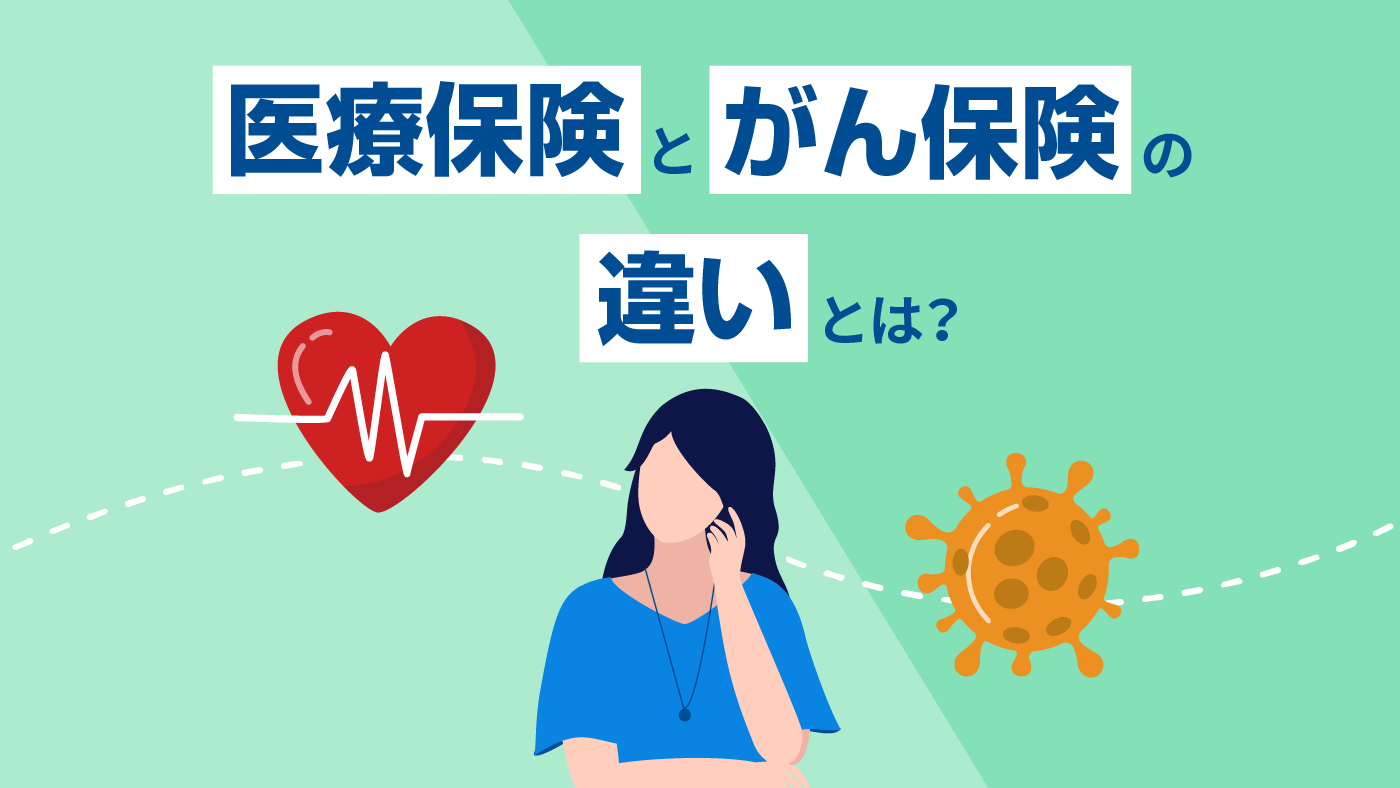「生命保険に入ろうと思うけど、難しくて迷う」「自分が加入している生命保険の契約内容がよくわからない」という人は多いのではないでしょうか。
この記事では、生命保険の主な種類やそれぞれのメリット・デメリットを紹介します。あわせて、どうすれば自分に合った生命保険に過不足なく加入できるのかも解説しますので、参考にしてください。
目次
- 生命保険とは?
- 3種類の生命保険の違いとは?
- 4種類の個人年金保険の違いとは?
- 過不足なく生命保険を活用するには?
- 生命保険とは死亡リスクや長生きリスクに備えるための保険
生命保険とは?
まずそもそも「生命保険」とはどのような保険なのか整理しておきましょう。
生命保険は、広い意味では「人に対してかける保険全般」を指します。
たとえば、保険をかけられている人(被保険者)が亡くなったときにお金を受け取れる「死亡保険」、満期まで生きていた場合にお金を受け取れる「生存保険」をはじめ、病気やけがの際に役立つ「医療保険」や「がん保険」なども生命保険の仲間です。

ただ、上記のうち死亡保険だけを指して生命保険と呼ぶこともあります。広い意味と狭い意味、どちらでも使うので混乱しないよう注意しましょう。この記事では、死亡保険や生存保険など「生命」に関するリスクに備える保険全般を生命保険と呼んでいます。
生命保険に加入することで、万が一死亡した場合や長生きした場合のリスクに備えることができます。
3種類の生命保険の違いとは?

生命保険にはいくつもの種類があります。それぞれ契約期間や保険金を受け取れるタイミングなどが異なるため、正しく理解して、自分が望む保険を選択することが大切です。
ここでは、主な3種類の生命保険の特徴や違いについて解説します。
割安な保険料で大きな保障が得られる『定期保険』
定期保険とは、加入できる「期」間が「定」められている、つまり満期があるタイプの死亡保険のことです。「期間内に亡くなったら○万円受け取れる」といったシンプルな保障が特徴です。

定期保険は保険料がいわゆる「掛け捨て」で、割安に加入できます。
一般的に、扶養している家族が多い人や幼い子どもがいる人など、もし万が一のことがあったときに家族が経済的に困窮する可能性が高い人ほど、死亡保険の保険金を高くしてしっかり備えておいた方がよいといわれています。
定期保険なら、しっかり加入しても保険料の負担が比較的少なく、子どもが独立するまでなど「必要な期間だけ加入する」といった融通も利きやすいでしょう。
デメリットは、いつか満期が来て保障が切れることです。通常は更新も可能ですが、更新のたびに保険料が上がるうえ、年齢や健康状態などによっては更新できない場合もあります。
一生涯保障が続く『終身保険』
終身保険は、「身」が「終」わるまで、つまり一生涯ずっと保障が続くタイプの死亡保険です。前述の定期保険と違い、自分から解約や変更をしない限り、ずっと同じ保険料のまま一生加入し続けることができます。
また、終身保険は保険料が「掛け捨て」ではありません。保険料の一部が積み立てられていき、解約時にはまとまった金額の解約返戻金として受け取れるため、貯蓄性があります。

終身保険のメリットは、長く安心が続き、亡くなったときも亡くならずに保険が不要になったときも役に立つ点です。
しかし反面、定期保険と比べて保険料が割高なため、毎月の保険料負担が重くなりやすい点がデメリットです。
満期保険金と死亡保険金が同額の『養老保険』
養老保険は、定期保険と生存保険を合わせたような特徴を持ち「生死混合保険」とも呼ばれています。
つまり、満期があり、それまでに亡くなった場合は死亡保険金を、亡くならずに生存した場合は満期保険金を受け取れる保険です。基本的に、死亡保険金と満期保険金が同額なのも大きな特徴です。

養老保険は、1つの保険で死亡と長生きの両方のリスクに備えられる点がメリットです。終身保険同様、貯蓄性があるため、途中で解約した場合は解約返戻金が受け取れます。
デメリットは、終身保険よりも保険料が割高で、満期後は保障がなくなる点です。前述の2種類ほどメジャーではないため、取り扱っている保険会社が少なめな点も不便に感じるかもしれません。
4種類の個人年金保険の違いとは?
個人年金保険とは、老後に向けて保険料の一部を積み立てていき、時期が来たら年金として受け取れるしくみの保険です。生存保険の一種で、保障よりも貯蓄性や資産形成を重視する人によく選ばれます。
個人年金保険では、個々の希望に合わせてさまざまな受け取り方を選択できます。受け取り期間などによっていくつかの種類に分類されますが、ここでは主な4種類の特徴や違いについて解説します。
一定期間、被保険者の生死に関係なく年金を受け取れる『確定年金』
個人年金保険の「確定年金」とは、年金を受け取れる期間が「確定」しているタイプを指します。本人が亡くなっていても、生きていても、あらかじめ定められた期間内はずっと年金が受け取れます。

本人が亡くなっても家族が年金を受け取れることと、受け取り期間があらかじめ明確になっていることが大きな特徴です。長期的な家計の見通しが立てやすく、期間中は本人が亡くなっても遺族が年金を受け取ることができるので、損にはなりにくいでしょう。
デメリットは、受け取り期間が「5年」「10年」「15年」などと決まっていて、その期間が終了したあとは何も受け取れなくなることです。
一生涯年金を受け取れる『終身年金』
終身年金は、本人が亡くなるまで一生涯ずっと年金を受け取れるタイプです。国民年金や厚生年金といった公的な年金制度は、終身年金の代表格といえます。

終身年金のメリットは、どれだけ長生きしても、ずっと年金の受け取りを継続できる点です。長生きすればするほど受け取り総額が多くなり、お得になります。
一方、デメリットは保険料が割高な点です。また、早期に亡くなってしまった場合は受け取り総額が少なくなります。
個人年金保険の中には、「保証期間付終身年金」という種類もあります。これは一定期間(保証期間)のあいだは本人の生死にかかわらず年金を受け取れ、その後は本人が亡くなるまで受け取れる、確定年金と終身年金の中間のようなタイプです。

一定期間のみ被保険者が生きていれば年金を受け取れる『有期年金』
有期年金は、受け取り期間があらかじめ決まっていて、その中で本人が生存している間だけ年金を受け取れるタイプです。

有期年金の受け取り期間は、確定年金同様「5年」「10年」「15年」など契約時に決めた期間となっています。
有期年金のメリットは、前述の年金タイプと比べて割安な保険料で加入できる点です。デメリットは、終身年金より受け取れる期間が短く、早期に亡くなると受け取り総額が少なくなる点です。
中には「保証期間付有期年金」として、一定の保証期間の間は本人が亡くなっていても年金が受け取れるタイプの有期年金もあります。早期に亡くなった場合のデメリットを緩和できますが、その分、保証期間がないタイプより保険料が割高になりやすいです。
夫婦のいずれかが生存している限り年金を受け取れる『夫婦年金』
夫婦年金とは、夫婦のうちのいずれか一方が生存していれば年金を受け取れるタイプです。
確定年金や保証期間付終身保険として契約し、年金の受け取りを開始したときに夫婦年金に変更するのが一般的です。
夫婦年金のメリットは、本人が亡くなっても配偶者が生きている限り年金の受け取りを継続できる点です。「早期に亡くなったために受け取り総額が少なくなって損をする」というリスクを軽減できるでしょう。
夫婦年金ならではのデメリットとして、離婚した場合に手続きが面倒になる点が挙げられます。保険契約の解約や変更が必要になり、結果的に損をしてしまう可能性もあります。
過不足なく生命保険を活用するには?
生命保険にはさまざまな種類があり、保険金の金額や受け取り方を自分で決めることができます。自由度が高い分、どんな保険にどれくらい加入すべきなのか迷ってしまうかもしれません。
自分に合った生命保険を過不足なく選ぶには、どうすればいいのでしょうか。
加入目的、保障を必要とする期間、金額を明確にしよう
「心配だからとりあえず保険に入る」「保険をなんとなくで選ぶ」という行動が、保険のかけすぎの原因となることが多いです。
まずは保険に加入する前に、どのような万が一に備えて、いつまでの期間、どれくらい保険による保障が必要なのか整理してみましょう。
たとえば、老後が心配な50代独身の人と、子どもの将来が心配な30代夫婦では、保険の加入目的が違うため選び方も変わってくるでしょう。
保険の必要性は家族構成や家計の状況、年齢や価値観などによっても異なり、個人差が大きいため「自分の場合はどうなのか」を明確にしておくことが重要です。
社会保障など既にある保障を正しく把握しよう
過不足なく保険に入るには、国や自治体が用意している「社会保障」や勤務先が用意している「企業保障」など、すでに準備できている保障について正しく理解しておく必要があります。
民間の生命保険にまったく加入していない状態でも、公的年金や健康保険、退職金などさまざまな制度によって守られています。なかには、社会保障や企業保障が充分手厚く、民間の保険が不要な人もいます。
すでにある保障を把握したうえで、いくら足りないのか、貯蓄等でカバーするのは難しそうか事前に確認し、足りない分だけを保険で補うようにするのがおすすめです。
社会保障の内容については以下の記事で詳しく解説しています。
あわせて読みたい
生命保険以外の解決策と比較検討しよう
死亡リスクや長生きリスクに備える方法は、生命保険だけではありません。たとえば預貯金や資産運用などを行って、いざというときに必要な資金を確保しておくのも1つの方法です。
特に、長生きリスクが顕在化するのは定年退職や老後を迎えたタイミングなので、早いうちからコツコツと資産形成していけば充分間に合う可能性が高いです。
投資信託などの金融商品で運用すれば、預貯金より早く多くの資金を確保しやすくなるでしょう。近年はNISAやiDeCoといった投資に関する税制優遇制度もあるので、活用を検討してみましょう。
あわせて読みたい
定期的に生命保険を見直そう
「保険で備えておくべき金額」は、時期によっても異なります。たとえば、子どもが生まれたばかりの時期と社会人になった後では、家族を今後養っていくために必要な金額が大きく異なるため、保険で備えておくべき金額も変わるでしょう。
生活環境に変化があったときは、生命保険を見直すタイミングです。一度加入したらそれきりではなく、適宜見直して、過不足のない状態を保ちましょう。
基本的に、独身のあいだは保障を少なく、結婚して子供が生まれたら手厚くし、子どもが社会人になったら再び保障を少なくする(もしくは止める)とよいと言われています。その他、一定以上の貯蓄ができたら貯蓄でカバーできる分の保障額を下げる、住宅ローンを組んだら団信でカバーできる分の保障額を下げるといった工夫もできます。
生命保険とは死亡リスクや長生きリスクに備えるための保険

生命保険とは、亡くなってしまったときや長生きして老後を迎えたときの経済的なリスクに備えるための保険です。また、保険には、一括で受け取る方法以外にも年金形式で受け取る方法などバリエーションが豊富な受け取り方が用意されています。個々のニーズに合わせた受け取り方を選択できる点も、生命保険で備えるメリットといえるでしょう。
さらに、生命保険には、終身保険や定期保険などさまざまな種類があるため、内容をよく理解したうえで加入する必要があります。どの時期に、いくらくらいのリスク(資金不足が生じる可能性)があるのかを明確にしてから検討するのがおすすめです。