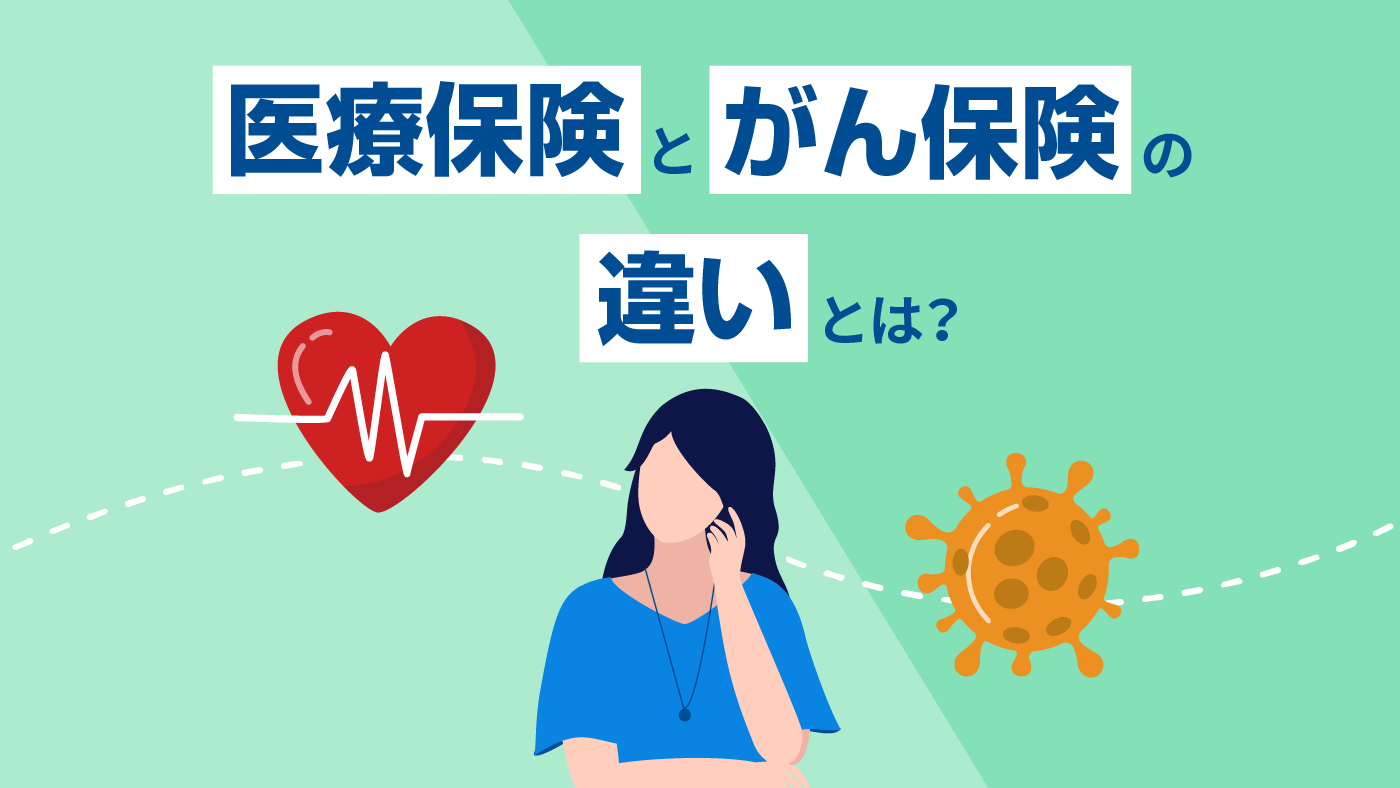人生には、さまざまなリスクがあります。病気やけが、事故や天災など、心身の健康や財産が脅かされる可能性はいろいろなところに潜んでいるため、リスクをゼロにすることはできません。しかし、どのようなリスクがあるのか把握して、事前に備えておくことはできるはずです。
この記事では、人生の中でも特に大きなリスクにはどのようなものがあるのか、どうやって備えるべきなのか解説します。
目次
- 人生の主なリスクとは?
- 人生のリスクに備える方法は?
- 各リスクに備えるにはどの保険を検討すべき?
- 保険を検討する前に|公的保障でカバーできるリスクとは?
- 企業保障でも人生のリスクに備えられるのか?
- 日頃からの心がけでリスクを下げることもできる
- 人生の主なリスクには貯蓄や保険で備えることができる
人生の主なリスクとは?
人生におけるリスクには、たとえば以下のようなものがあります。
- 死亡するリスク
- 大きなけがや病気をするリスク
- 働けなくなるリスク
- 長生きするリスク
- 介護が必要になるリスク
- 天災のリスク
- 交通事故の加害者になるリスク
これらがなぜ人生の中でも特に大きなリスクと言えるのか、具体的に解説します。
死亡するリスク
「死亡」は言うまでもなく、大きなリスクです。亡くなる本人はもちろんですが、残される家族にとっても同様です。
家計を支えていた人が急に亡くなったような場合には、遺族が精神的にも経済的にも追い詰められてしまうことがあります。配偶者や子どもなどを養っている場合は特に、遺族の生活を守るための備えについて検討しておきたいところです。
厚生労働省の「令和4年度簡易生命表」によれば、60歳までの死亡率は男性7.2%、女性4.2%です。死亡リスクは年齢とともに高まりますが、働き盛りのうちに死亡するリスクは決して高くありません。
大きなけがや病気をするリスク
大きなけがをしたり、重い病気が見つかったりするリスクもあります。場合によっては手術や入院などが必要になり、多額の医療費がかかるかもしれません。
生命保険文化センターの「2022年度生活保障に関する調査」によれば、過去5年間に入院経験がある人は16.7%でした。
その人たちに、直近の入院時の自己負担費用と入院によって失った収入の合計額を尋ねたところ、平均は26.8万円でした。その中で50%以上が20万円未満であり、入院日数が長くなればなるほど合計額は高くなるという結果になっています。
働けなくなるリスク
病気やけがなどの状況によっては、今までどおり働けなくなるかもしれません。しかし、働けなくなったとしても、自分や家族は生活していかなければならないため、医療費や生活費などの出費は続きます。
前述の「死亡するリスク」同様、家計をおもに支えている人は特に、このリスクに備えておく必要があるでしょう。
長生きするリスク
長生きは喜ばしいことです。ただ、高齢になって収入が下がった状態で、現役時代と同程度の生活費がかかっているなど赤字の状態が続くと、資産が底を付くリスクが考えられます。過去には「老後に2,000万円不足する」という金融庁の試算が世間を賑わせたこともありました。
老後のお金について、漠然とした不安を抱える人は多いでしょう。何歳まで生きても安心して暮らせるよう、計画的に備えておきたいところです。詳しくは後述しますが、退職金や年金など受け取れる金額を予測しておくことも大切です。
介護が必要になるリスク
高齢になるにつれ、介護が必要になるリスクも上がります。要介護状態になると働いて収入を得ることが難しくなるうえ、介護サービスを利用するのにお金がかかります。自分が要介護状態になったときだけでなく、親や家族がそうなった場合のリスクもあります。
厚生労働省の「介護給付費等実態統計(令和元年9月審査分)」によると、介護が必要な状態と認定された人の割合(要介護認定率)は85~89歳で50.2%、90歳以上は75.9%となっています。人生100年時代には、介護は他人事ではありません。
天災のリスク
日本に住んでいる以上、地震や台風などの自然災害に巻き込まれるリスクは避けられません。また、自宅や近隣で火事が発生する可能性も考えられます。
天災や火災によって自宅などが被害を受けると、再建のための費用が数千万円単位でかかるなど、家計へのダメージがかなり大きくなる可能性が高いでしょう。
交通事故の加害者になるリスク
事故の被害者になるリスクだけでなく、意図せず加害者になってしまうリスクもあることを知っておきましょう。仮に交通事故を起こした場合、多額の損害賠償金の支払いを命じられる可能性があります。
自動車だけでなく、自転車でも事故は起きます。過去には、自転車に乗っていて事故を起こした加害者(小学生)の母親に対して、約9,500万円の損害賠償が命じられたこともあります。
人生のリスクに備える方法は?

上述のような人生のリスクの経済的な側面に対して、自分で備える方法はおもに以下の2種類です。
- 貯蓄
- 保険
それぞれのメリット・デメリット、注意点を紹介します。
貯蓄で備える
もしものとき、充分な貯蓄は強力な味方になってくれます。お金があれば、ひとまず窮地をしのぐことも、選択肢の幅を広げることもできるでしょう。
特に銀行などに置いている預貯金は、いつでもすぐに使える(流動性が高い)うえ、使い道も自由なので、緊急時にも対応しやすいというメリットがあります。もちろん、万が一のことが起こらなかったときにも役立ちます。
一方で、預貯金の利回りは低く、物価上昇に弱いのがデメリットです。預けていてもお金が増えにくいので、値上げの波についていけず、実質的に資産が目減りする可能性もあります。
物価上昇にも負けないよう、資産運用を行うという選択肢もあります。預貯金よりも効率よくお金を増やせる可能性がある一方で、運用に失敗すると損失が出ることもあります。備えとして活用するなら、過度にハイリスク・ハイリターンな金融商品や投資手法には手を出さず、リスクを抑えて堅実に運用するのがおすすめです。
保険で備える
もう1つ、経済的なリスクに備える方法として有効なのが「保険」です。
貯蓄で備える場合、充分な金額を確保するまでに少なからず時間が必要です。しかし保険は、貯金が苦手な人でも、収入が少ない人でも、契約すればすぐに大きな保障を確保できます。掛け捨て保険などを活用すれば、少額の負担で大きな保障を得ることも可能です。
ただ、貯蓄と違って、コスト(保険料)がかかる点はデメリットです。また、保険によっては、途中で解約すると目減りするものもあるので注意しましょう。低金利時代の保険は利回りが低いため、貯蓄同様、物価上昇に弱いというデメリットもあります。
各リスクに備えるにはどの保険を検討すべき?
一口に「保険」といっても、種類が多すぎてよくわからないという人もいるでしょう。
備えたいリスクごとに、適した保険が異なります。以下の表で確認しておきましょう。
| 主なリスク | 対応する保険 |
|---|---|
| 死亡 | 終身保険、定期保険、養老保険、収入保障保険(家族収入保険)など |
| 病気・けが | 医療保険、がん保険、傷害保険、業務上の場合は労働災害総合保険など |
| 失業・休業 | 所得補償保険、就業不能保険など |
| 老後 | 個人年金保険など |
| 介護 | 介護保険など |
| 天災 | 火災保険、地震保険など |
| 交通事故 | 自賠責、任意加入の自動車保険など |
民間の保険会社が提供している保険商品だけでも、上記のとおりさまざまな種類があります。 基本的に、契約で決められた事象が発生したときに、決められた金額を受け取れるしくみになっています。
それぞれの保険の内容や選び方は、以下の記事で詳しく解説しています。
保険を検討する前に|公的保障でカバーできるリスクとは?

前述の保険を検討する前にぜひ知っておきたいのが、公的保障の存在です。
民間の保険に加入していなくても、すでに国の制度によって守られている状態になっています。保険を選ぶときはそれを考慮して、公的保障で足りない部分だけを補うように加入するのがおすすめです。
前述の主なリスクのほとんどに、対応する公的保障があります。
| 主なリスク | 対応する公的保障 |
|---|---|
| 死亡 | 遺族年金など |
| 病気・けが | 公的医療保険(健康保険)、業務上の場合は労災保険(労働者災害補償保険)、障害年金など |
| 失業・休業 | 雇用保険、健康保険の傷病手当金など |
| 老後 | 老齢年金など |
| 介護 | 公的介護保険、介護休業給付など |
| 天災 | 災害弔慰金、災害援護資金貸付など |
民間の保険と違い、公的保障は加入義務があります。原則として、年齢などの条件を満たした人は、給与からの天引きなどで保険料を納めて加入しています。
民間の保険と同じように万が一の時にお金を受け取れる制度もあれば、そもそもの支払い額を抑えられる制度もあります。
それぞれの保障の内容は、以下の記事で詳しく解説しています。
あわせて読みたい
企業保障でも人生のリスクに備えられるのか?
民間の保険と公的保障のほか、勤務先によっては、福利厚生の一環として独自の保障(企業保障)を用意している場合があります。
企業保障の有無や内容は勤務先によって異なりますが、たとえば下記のような保障がある可能性があります。
| 主なリスク | 対応する企業保障 |
|---|---|
| 死亡 | 死亡退職金、遺族年金、企業年金など |
| 病気・けが | 療養見舞金など |
| 失業・休業 | 法定外労働災害補償など |
| 老後 | 退職金、企業年金など |
| 介護 | 介護・看護休職制度など |
| 天災 | 災害見舞金など |
上記のような保障があれば、万が一の際もより安心できるでしょう。
企業保障の内容は、勤務先の就業規則や、加入している健康保険組合の公式サイトなどで確認できます。
普段はあまり意識することがないかもしれませんが、企業によってかなり差があるうえ、もしものときや保険選びの際に影響するため、一度じっくりと調べてみるのがおすすめです。
日頃からの心がけでリスクを下げることもできる
ここまで紹介した私的保障(貯蓄や民間の保険)、公的保障(国や自治体による保障)、企業保障(勤務先による保障)以外にも、人生のリスクに備える方法はあります。
それは、リスクそのものを下げるための日頃の心がけです。
病気やけが、介護のリスクを抑えるために健康管理に気を付ける、安全運転に努める、老後も収入を得られるように体力やスキルを身に付けておくなど、できることはたくさんあります。
人生の主なリスクには貯蓄や保険で備えることができる

人生にはさまざまなリスクが潜んでいます。経済的に大きなダメージを被るような主なリスクには、貯蓄や保険で備えておくことができます。
ただ、解決策はそれだけではなく、健康管理や安全管理など日頃からの心がけでもリスクを下げられます。
いざというときに役立つ公的保障や企業保障もあります。万が一のことが起きる前に、自分や家族にはどのような保障があるのか、理解を深めておきましょう。